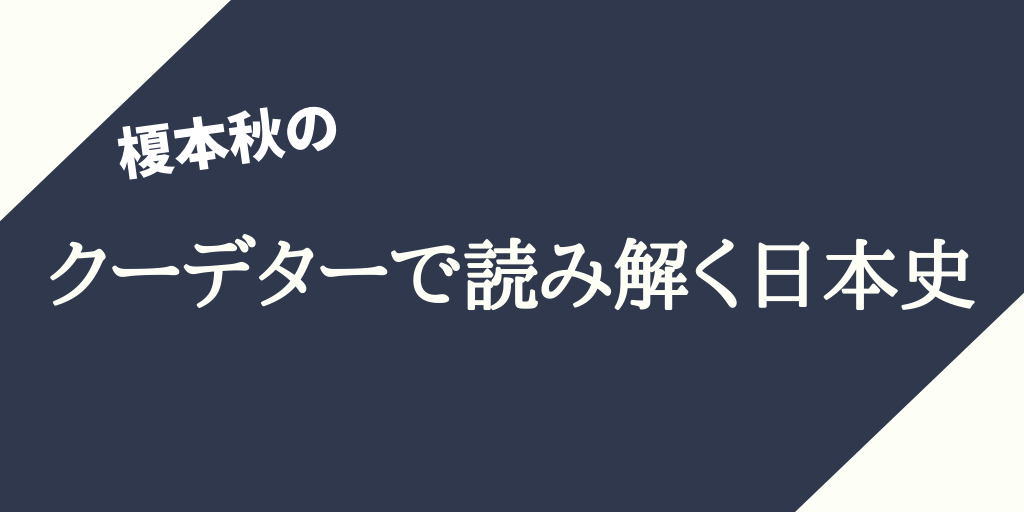
1177年(治承元年) ○平氏 ×後白河法皇の近臣
保元の乱と平治の乱後、後白河上皇と手を組んでさらに勢力を拡大した平清盛ら平氏は、政治にも口を出せるほど力をもった一族となっていた。清盛は貴族としての最高位である太政大臣にまでなっている。
しかし急速な勢力拡大が既存の貴族たちから反感を買ったのは事実だ。また、平氏の傲慢な振る舞いが反発を招いた部分もあるようだ。
『平家物語』などにも記されている事件に、「殿下乗合事件(でんかののりあいじけん)」というものがある。
ある時、清盛の孫である資盛(すけもり)と摂政の松殿基房(まつどの もとふさ)が往来で行き会ったのだが、資盛は目上の貴族(相手は摂政)に対する当然の礼儀である「馬から下りる」行為を行わなかった。これに怒った基房の従者たちが資盛の車などを破壊してしまう。
貴族の流儀で考えれば非のあったのは資盛のほうということになりそうなものだが、相手は平氏である。基房は揉め事を避けるために資盛の父である重盛(しげもり)に謝罪しようとしたが受け入れられず、仕返しを食らってしまう。
結局基房が再度の仕返しを行うことはなかったのでこの一件はこれで終わったが、平氏の傲慢さを示す象徴的な事件といっていいだろう。
さらに、清盛と後白河上皇が協力体制にあったといっても、それぞれの権力確立を目指す両者の利害関係は究極的には対立していた。
その間を取り持つ存在として後白河上皇に寵愛された建春門院(けんしゅんもんいん=清盛の妻、二位尼の妹)という女性がいたのだが、彼女の死後には両者の関係は確実に悪化していく。
そんな中の1177年(治承元年)、平氏への敵意がむき出しになったのが、京都東山にある鹿ヶ谷山荘で行われた密会である。
後白河法皇(この頃には出家していた)の側近である藤原成親(ふじわら の なりちか)、成経(なりつね)、師光(もろみつ=西光)、僧・俊寛(しゅんかん)といった人々が平氏を倒そうと密かに話し合いをしたのだ。
この一件については「酒が入った中での戯言であった」ともいうのだが、密告者からこのことを知らされた清盛は容赦しなかった。主要人物たちを捕らえ、拷間の末に殺害したり、あるいは配流先で殺してしまったりした。
これによって側近の多くを失った後白河法皇の勢力は少なからず後退したのだ。
――そして、この陰謀については、「実は清盛のでっち上げだったのではないか」という見方がある。
実はこの頃、後白河法皇は西光の子どもたちが起こしたトラブルのせいで比叡山延暦寺と深刻な対立を抱えており、これを解決させるために清盛に命じて延暦寺を攻撃させようとしていたのである。当時の宗教勢力は宗教的権威と武力を併せ持った存在であり、これと喧嘩してもいいことは何もなかった。しかし法皇の命令に理由なく背くこともできない。平氏は危機に陥っていたのだ。
ところが、まさに平氏の軍勢が出陣するか、というタイミングになって「鹿ヶ谷の陰謀」が発覚。実はこのことも平氏と延暦寺を噛み合わせて弱ったところを叩こうという陰謀だったのだ、ということになったのである。もちろん、出陣はとりやめとなった。
つまり、清盛は邪魔な後白河法皇の側近たちを排除しつつ、断りづらかった命令を断る大義名分を獲得したのである。まさに一挙両得というわけで、実は陰謀などというものはなかったのではないか、とかんぐる声が出てくるのも当然といっていいだろう。
この事件の後、清盛の娘と高倉天皇(後白河法皇の子)の間に生まれた子が安徳天皇として即位するが、このことはむしろ清盛が後白河法皇に頼らずとも政治的権威を手中に収められるようになったともいえ、両者の対立はさらに加速していった。
結果、清盛は1179年(治承3年)に武力によって後白河法皇を幽閉。権力を平氏一族の元に集中させる。だが、このことはむしろ反平氏勢力を増やすことにつながり、「平氏にあらずば人にあらず」という言葉まで生み出した平氏の隆盛は一気に終焉を迎えることになるのだった。