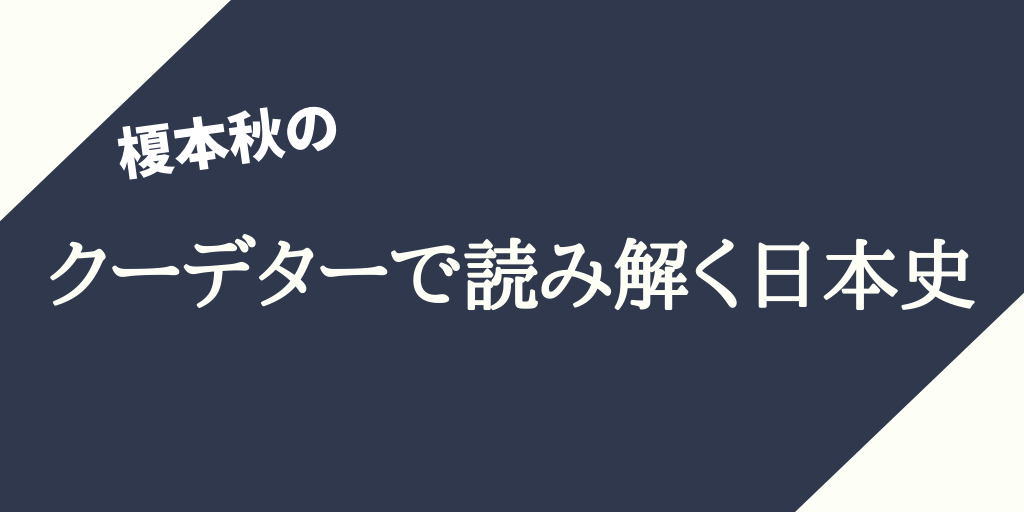
1701年(元禄14年)~1703年(元禄16年) ○浅野長矩の家臣 ×吉良義央
5代将軍・徳川綱吉(とくがわ つなよし)の時代に起きたのが元禄赤穂事件(げんろくあこうじけん)――後世の創作の名をとって「忠臣蔵(ちゅうしんぐら)」事件としても知られる一連の出来事である。
発端は1701年(元禄14年)2月、江戸城内の松之廊下において浅野長矩(あさの ながのり)が「遺恨、覚えたか」と叫んで吉良義央(きら よしひさ)に切りかかったことだった。
城内で刀を抜くことはご法度であるため、理由を詳細に聞かれることもなく長矩は切腹を命ぜられ、そのまま自刃している。一方、傷を負った吉良上野介義央はおとがめなしであった。
このような事情から、今日でも長矩が刀を抜いた理由ははっきりとは分かっていない。
一般には「朝廷からの勅使接待を命じられた長矩が、各種儀礼を司る高家(こうけ)の義央に教えを求めたところ賄賂を要求されたことが原因」という説が有名だが、ほかにも「長矩が精神的な問題を抱えていた」「義央が浅野夫人に恋慕していた」「赤穂藩の特産品である塩をめぐるいさかい」などと多様な説が存在し、すべて推測の域を出ない。
この事件を受けて、赤穂藩浅野家は取り潰しとなった。
城を明け渡すか徹底抗戦するかについては藩内で論争になったが、家老の大石内蔵助良雄(おおいし くらのすけ よしお)が中心となって主張したとおり、おとなしく幕府へ明け渡すことになった。
また、今後の方針の話し合いが行われた結果、「申し開きの機会さえ与えられぬまま果てた君主の不名誉を削ぐため、吉良に復讐をしよう」とする意見もあったが、現実的に再就職を望む声や、長矩の弟である浅野大学(あさの だいがく)による赤穂藩再興の目がこの時点ではまだあったため、しばらくは様子を見ることになった。
やがて大学の広島配流が決定されて再興が不可能になると、彼らは討ち入りを決断する。1702年(元禄15年)12月14日当日、47人のもと赤穂藩士が吉良邸に乱入して台所に潜んでいた義央を打ち取ることに成功する。
吉良邸を引き上げた一行は浅野家の菩提寺である泉岳寺へと向かった。ここには亡き君主である長矩の墓があり、その墓前に吉良の首を供え、敵討ちを果たしたことを報告したとされる。
自首した彼らの扱いについては幕府内でも少なからずもめたらしい。
「主君の仇を見事に取った義士である」として助命を訴える声があったのである。それでも「法を破ったことは罪である」とする声のほうが強く、せめて武士としての立派さを讃えて切腹という名誉ある死を与えることによって決着した。吉良家に対しても領地没収の処罰が下っており、このことが浪人たちに伝えられたこととあわせて、彼らの慰めになったかもしれない。
さらに、庶民たちは彼らの忠義の心を大いに賞賛し、また幕府の裁定に武力を持ち込んで私的闘争をすることによって自らの価値観を貫き、逆らったという反権力的な姿勢がうけて、以後長く各種フィクションの題材として人気を博すことになる。
なぜそれほどまでに人気が出たのか。その背景にはこの時代の政治があったのではないか、と考えられる。
綱吉の統治は彼が傾倒した儒学を根幹とする文治政治(ぶんちせいじ)であった。彼は世に名高い生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい=生き物の殺傷を禁じる一連の法令)や服忌令(ぶっきりょう=身近な人間が死んだ時に喪に服し、穢れを払うために謹慎することを制定)を通して、まだ世間に残っていた戦国時代以来の中世的価値観――人を殺すことや人の死に強烈な禁忌を感じず、武力によって自分の意思を通すことが決して悪ではない、とする考え方を転換させようとしたらしい。いわゆるかぶき者(一般的スタイルからはみ出した無頼漢たち)の排除もその一環だろう。
しかし、天下泰平の時代にあろうと、やはり支配階級である武士たちは本来軍人であり、「戦うことによって存在意義が満たされる」「誇りを武力によって全うせねばならない」という価値観は根強くあったはずだ。
綱吉の政治はそれと相反するものであり、武士たちおよび彼らと価値観を共有する庶民たちは少なからず反発を募らせていたのではないか。
そうした綱吉の政治に対する反発の具現こそがこの元禄赤穂事件であり、それに対する体制側の返答こそが「武士としての誇りは認めるが、しかし犯罪であることに変わりはない」という切腹処置だったのだろう、と考えられるのだ。