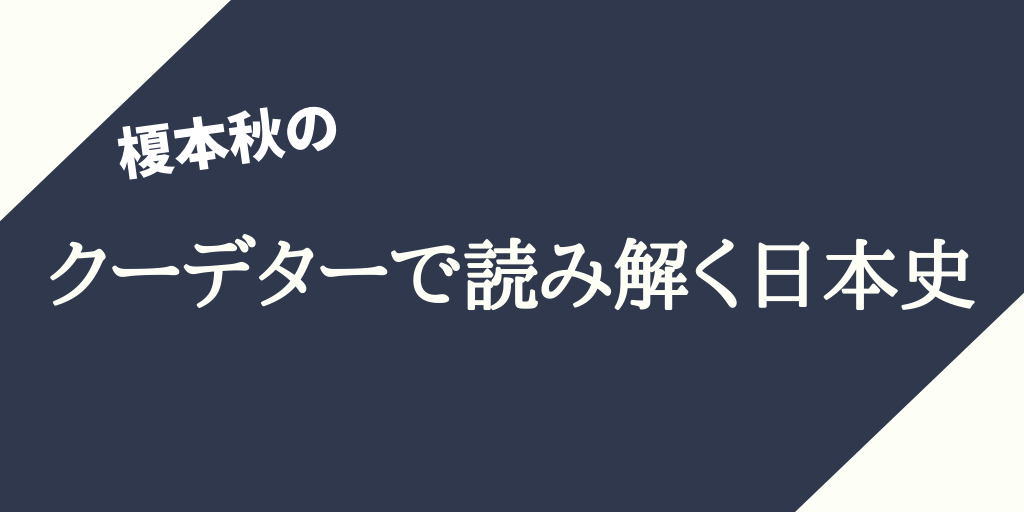
1028年(長元元年)○源頼信 ×平忠常
関東における承平・天慶の乱が「新皇」平将門の死で終わった後も、この地域には高望王(たかもちおう)の子孫である桓武平氏が勢力を広げ、また小競り合いを続けていた。
そのうちのひとり、平忠常(たいら の ただつね)は上総の国司だったこともある人物だが、1027年(万寿4年)には当時の上総国司と戦いを始めて内乱状態に突入、翌年には上総国府を攻め落とし、また安房守・平惟忠(たいら の これただ)を殺すなど、房総地域に勢力を広げていた。
平将門の例を見るまでもなく、国司を殺し、国府を攻めるのは国家に対する反逆行為である。
朝廷は会議を行い、平直方(たいら の なおかた)と中原成通(なかはら の なりみち)に忠常討伐を命じた。ところが忠常は強く、二年にもわたって討伐軍を退け続けた。この間、成通が「状況報告をしていない」として解任され、また安房守・藤原光業(ふじわら の みつなり)が忠常の圧力に抗しきれず京へ逃げ戻るなど、状況は芳しくなかった。
そこで、当初の会議においても追討使(討伐軍指揮官)候補として名の挙がっていた源頼信(みなもと の よりのぶ)に白羽の矢が立った。
この人物は摂津に勢力を広げた源満中(みなもと の みつなか)の子で、かつて忠常を服従させたことがあり、関東の事情にも詳しかった。しかも、実はもともと忠常と対立状態にあり、国の命による討伐を大義名分に私戦を戦っていたふしのある直方と違い、頼信には強い利害関係がなかった。直方による実質的な私戦を認めたことで内乱の長期化を招いたことへの反省が、新たな追討使として頼信を選ばせたのだろう。
ただその一方で、この平忠常の乱における追討使選定については、摂関家をはじめとする貴族たちによる政治的駆け引きの面があったことも見逃せない。
最初に選ばれた直方にせよ、次に選ばれた頼信にせよ、以前から特定の貴族とのつながりがあり、また積極的な働きかけがあって、その結果として追討使に選ばれたのではないか、という指摘があるのだ。
これは、当時の武士たちにまだ政治力がなく、貴族に仕えて武力を提供する存在であったことを明確に示すものと考えていいだろう。彼らが独立した存在として活動するには、まだ時間を必要とする。
さて、頼信による平忠常討伐はどうなっただろうか。実は両者の間に戦いが行われることはなく、忠常はあっさりと降伏。京への道中で病没してしまったので、その首だけを携えて頼信は京に戻ったとされる。
二年にもわたる泥沼の内乱から、なぜこのようにスピード解決が果たされたのか。これはその二年の泥沼自体が原因であったらしい。房総地域はすっかり荒れ果ててしまい、人の心も忠常から離れていた。これではもう戦えない、という判断だったようなのである。
頼信は摂津源氏でも傍流の人間だったが、この戦いを契機に関東の武士たちに対して影響力を持つようになり、また京に近く東国にも睨みを利かせられる美濃守に任じられてこの地に自らの基盤を構築していく。
この一件は源氏の東国進出の端緒となったのである。