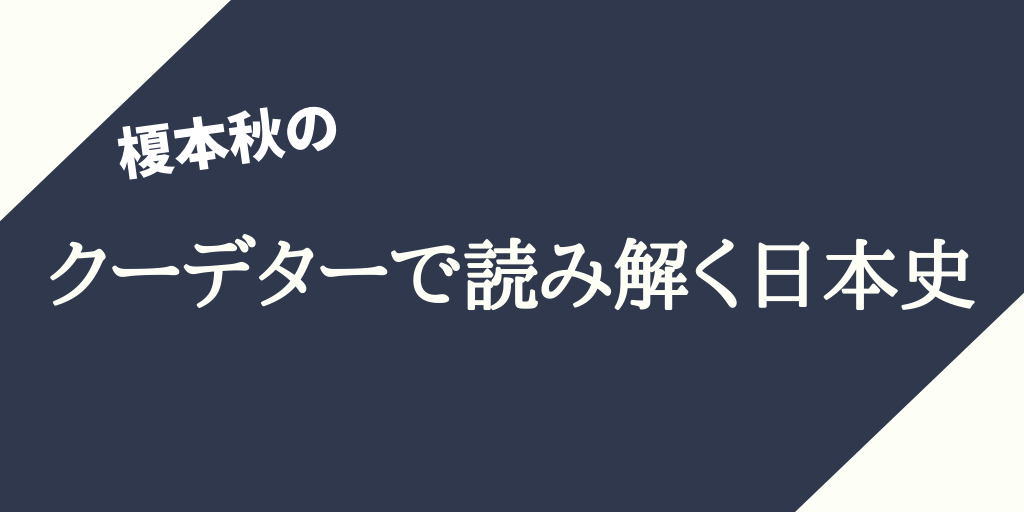
1051年(永承6年)~1062年(康平5年) 〇源頼義 ×安倍氏
前九年の役は続く後三年の役とあわせて東国への源氏の本格的進出と「武門の棟梁」の名声を確立させた戦いだ。
しかし、この戦いには重要な前段階がある。それは、反乱を起こして源氏によって鎮圧された安倍氏は俘囚(ふしゅう=朝廷に降伏した蝦夷)の大元締め的存在だったことである。桓武天皇の時代に大規模な蝦夷征伐が行われたのはすでに紹介したとおりだが、その後は俘囚たちによる自治が認められており、その中で安倍氏は陸奥国の奥六郡を実質的支配下に置き、さらにその外へも勢力を拡大しつつあったのだ。
これを危険視した陸奥守藤原登任(ふじわら の なりとう)が安倍氏の長・安倍頼良(あべ の よりよし)を攻めたものの敗れてしまったため、朝廷としては俘囚を抑え込むだけの武力を有した新たな陸奥守を決めねばならなかった。
そうして選ばれたのが平忠常の乱で活躍した源頼信(みなもと の よりのぶ)の子、頼義(よりよし)だったのである。
源氏と安倍氏の対峙は当初平和裏に進んだ。というのも、上東門院(じょうとうもんいん)彰子(しょうし)病気平癒祈願の大赦によって安倍頼良の罪が許されると、彼はそれ以上の反抗の意思を示さなかったからである。
頼義および彼の引き連れた東国武士たちの武名を恐れたという側面もあったかもしれないし、そもそも前陸奥守と戦ったこと自体が不本意なことで、なるべく中央政府と争いたくなかったのでは、という指摘もあるのだ。名前をわざわざ頼義から一字をもらって「頼時」と改めている辺りからも、そうした心情は透けて見えるだろう。
ところが頼義の陸奥守任期が切れる直前の1054年(天喜2年)、事件が起きる。
国府へ戻る途中の頼義一行が襲撃されたのだ。これに対し、頼義はすぐさま頼時の子、貞任(さだとう)を犯人と決めたつけたため、安倍氏の反発を買い、融和ムードは一変して合戦ヘと突入することになる。
先述したような安倍氏側の事情からすると、この展開には疑間が残る。彼らとしてはとにかく中央政府と争いたくなかったはずなのだ。長の子ともあろうものが、そんなデリケートな時期にこのような大事件を引き起こすだろうか?
一方、この時期にぜひ事件の種がほしかった人物がいる。誰あろう頼義だ。
彼の目的は安倍氏討伐によって武名を高め、勢力を拡大することであった、と考えられている。その挑発の一環としてこの殺傷事件は引き起こされた(あるいはでっち上げられた)のではないか。というわけだ。
このような経緯を経て始まった本当の意味での前九年の役は、なんと当初は安倍氏側優勢で戦いが進んだ。
頼義側の戦力は決して十分なものではなく、安倍氏追討の命令を朝廷から引き出すのにも手間取ってしまった。1057年(天喜5年)の7月には頼時を打ち倒すことに成功するが、同じ年の11月には貞任の猛攻の前に大敗、頼義はたった七人の部下に守られて命からがら撤退するところにまで追い込まれてしまったという。
その後も兵や物資の補給に苦しみ、苦戦を続けた頼義を救ったのは1062年(康平5年)、出羽における俘囚の長――つまり安倍氏と同じような立場にあった清原氏が援軍に駆けつけたことだった。
東北の事情に詳しい清原氏の軍勢は強く、なんとわずか1ヶ月で安倍氏を駆逐してしまった。こうして12年にわたって続いた前九年の役は頼義と清原氏の連合軍の勝利に終わったのである。
しかし、この戦いに真に勝利したのは頼義ではなく清原氏だったのでは、という見方もできる。
その根拠は、安倍氏追討に当たって頼義が就任していた、「鎮守府将軍」という東北支配の象徴的な意味の大きい職にある。これを戦後に継いだのが源氏ではなく、清原氏の清原武則(きよはら の たけのり)だったのだ。
結果、かつて安倍氏が占めた勢力をも奪い取って大いに躍進した清原氏であったが、そのことが清原氏内部における大規模な内乱――後三年の役へとつながってしまう。