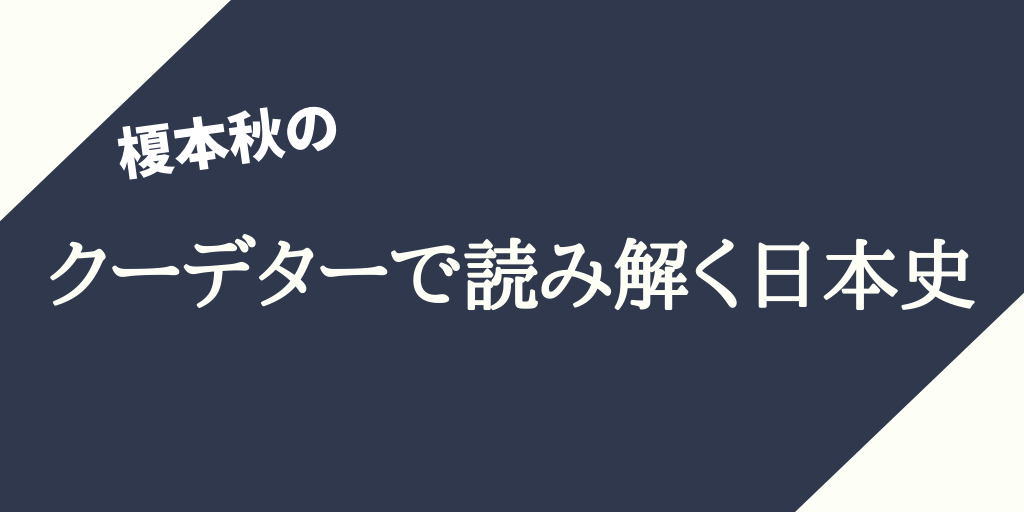
935年(承平5年)~940(天慶3年) ○朝廷 ×平将門・藤原純友
平安時代も後期に入ってくると、東国を中心とした各地方に武士団が成立し、中央政権にとっても無視できない力を持つようになってくる。
その背景にあった出来事は大きく分けて二つだ。
ひとつは荘園――寺社や貴族の私有地の登場である。
どうして彼らが広大な私有地を獲得するに至ったかといえば、十世紀頃より彼らが持つようになった特権の存在こそが最大の理由である。不輸・不入、つまり「国家に税も払わないし、役人も立ち入らせない」。
このような特権を持つ彼らの下に、各地の有力農民たちから「自分の土地を受け取ってくれ」と依頼が舞い込むようになる。そうすれば農民たちの土地も税が免除されるからだ。
こうした動きの結果、各地の有力民たちは力を蓄え、さらに武力までもって武士団を形成するようになったのである。
もうひとつは、地方に下向した役人が中央に戻らずに土着(あるいは中央と地方の両方に足場を築いて相互に往復する生活を形成)するようになったことだ。
彼らは中央での立場などを利用しつつ地方に大きな勢力を築き、また互いに争った。
このような流れの中で、ほぼ同じ時期に東と西で地方反乱が勃発する。この二つの事件を総称して承平・天慶の乱(あるいは首謀者の名をとって平将門・藤原純友(ふじわら の すみとも)の乱)という。
まず929年(天慶2年)に勃発した平将門の乱は、もともと一族内部の小競り合いに過ぎなかった。関東には高望王(たかもちおう=桓武天皇の曾孫で、関東に土着する)の子や孫にあたる桓武平氏一族が根を張り、勢力争いを繰り広げていた。
平将門はそうした親族と戦う平氏の一人だったのである。
この戦いが一族内部の私闘で終わらなかったのには、まずそもそも平氏一族の多くが地方役人もかねていたことがある。
役人を攻めるということはつまり国家を攻めるということにつながってしまうからだ。しかも、将門が力を増すにしたがって、地方役人と戦う各地の豪族たちがその勢力を頼りにして助けを求めるようになっていく。
彼がその要望に応えるということはつまり国家と戦うということにほかならない。さらに将門は「新皇」、すなわち新しい天皇を名乗って、人臣が踏み入ってはならない一線を越えた。結果、中央政府としては放置できない国家規模の反乱になってしまったのだ。
ことここに至って藤原忠文(ふじわら の ただぶみ)が征東大将軍に任ぜられ、討伐軍を率いて関東へ向かうことになる。
しかし、この戦いを決着づけたのはあくまで地方武士たちだった。将門に父を殺された平貞盛(たいら の さだもり=将門の従兄弟にあたる)と大百足退治の伝説で知られる藤原秀郷(ふじわら の ひでさと)が将門を攻撃し、その戦いの中で将門は流れ矢に当たって討ち死にしたのである。
ちなみに、この貞盛の子孫から後に平氏政権を樹立する平清盛ら伊勢平氏の一党や、鎌倉幕府の執権として実権を独占する北条氏が誕生している。
さて、この時期に西ではもう一つの反乱が起きていた。
940年(天慶3年)、藤原純友が瀬戸内海を暴れまわっていたのである。彼はもともと藤原北家の人間で、伊予に国司として赴任したのだが、やがて土着。瀬戸内海の海賊を支配下にして国家へ反逆した、というわけだ。
実は純友は926年(承平6年)には一度海賊行為をやめて国家への服従の姿勢を示しているのだが、また反旗を翻してしまった。それがちょうど将門の反乱と時をあわせているために「二人は東西で示し合わせて挙兵したのではないか」という推測が当時から根強く語られている。
しかし実際には両者が連絡を取り合っていた形跡などはなく、あくまで単独での反乱であったようだ。
純友は海賊ならではの機動力を用いて朝廷を翻弄したが、それも将門が倒れて政府が純友打倒に全力を傾けるまでだった。次々と勢力を削られて追い詰められた純友はついに討ち死にし、ここにようやく承平・天慶の乱は終結したのである。
このように将門・純友は善戦むなしく討ち死にしてしまったわけだが、彼らの残した爪あとは大きかった。
中央の貴族たちが「武士恐るべし」の印象を強くしたことで、中央においては貴族たちに欠けている武力を提供する存在として、また地方においては治安維持を行う軍事集団として、それぞれ重く扱われるようになっていったのだ。
これが後の武家政権の基盤となったことはいうまでもない。