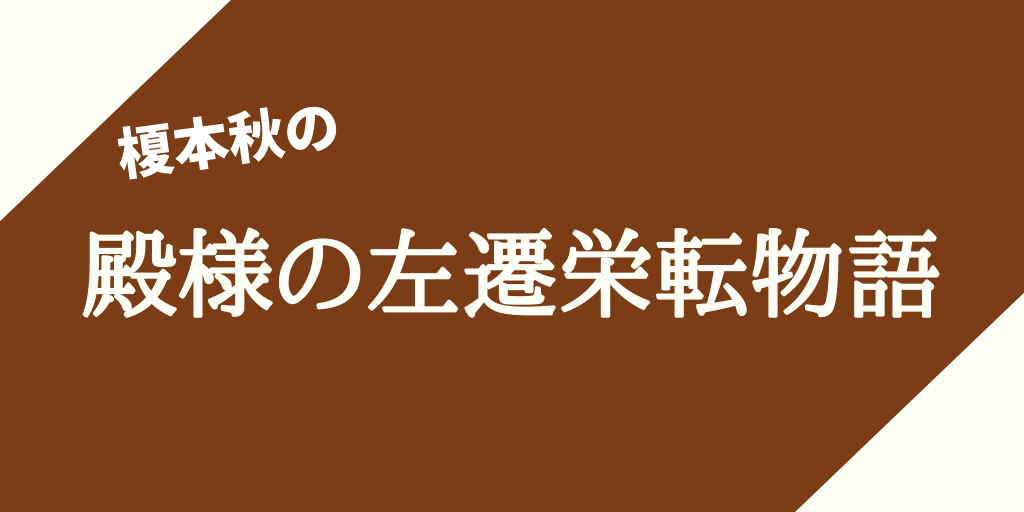
豊臣系外様大名たちの苦しい立場
福島正則と並んで秀吉子飼いの部下の代表格とされるのが、加藤清正である。彼はまた、築城術の名手としても名高く、熊本城はその代表作のひとつといえる。
藤原北家道長を祖とする加藤家は、その子孫が美濃に下った際に「加藤武者」と称したのが始まりとされているが、確証はない。
その後、11代・清忠が秀吉の母の従姉妹と結婚したため、息子の清正が秀吉のもとに預けられ、子飼いの家臣となったという。秀吉との姻戚関係についてもハッキリとわかっているわけではないのだが、清正が幼少期から秀吉に従い、成り上がり者であるために先祖代々の譜代を持たない秀吉の子飼いとなり、多くの功績を立てたことは間違いない。
豊臣政権において、清正は肥後国の熊本に19万5千石余を与えられた。
もともとは織田家臣時代の同僚である佐々成政が肥後に入ったが、検地をめぐって地元の国人たちと対立して大きな武力反乱を引き起こしてしまい、切腹に追い込まれてしまう。結局、鎮圧後に清正ともうひとり、小西行長が肥後に入って、この地を治めることになった。
関ヶ原の戦いが起きると、清正は東軍に与して九州の各地を転戦することになった。一方の行長は西軍に与して関ヶ原に出陣し、捕らえられて処刑されたので、清正は旧小西領のほとんどを与えられ、肥後一国(プラス豊後の一部)を領する、54万石の大大名となった。
このことからもわかるように、清正は豊臣恩顧の大名であると同時に、親・家康的な人物でもあった。そうした彼の立場をうかがわせるエピソードがある。
ある時、福島正則が同じく豊臣恩顧の大名である池田輝政(家康の娘を妻に迎え、「神君の婿」と呼ばれた)に幕府による自分たち外様大名の扱いを愚痴ったことがある。
城作りに酷使されて大変だ、お前は家康の婿なんだからどうにか話してくれないか、と。輝政としても豊臣家と関係が深いために微妙な立場であり、どうこういえるはずがない。そこに、横で聞いていた清正が「そんなことをいうなら、国に帰って謀反の準備をしろ」といった、と伝わる。
つまり、外様大名たちに江戸城をはじめとする徳川家の城作りをさせるのは、彼らの力をそぐための幕府の政策であり、徳川家に従う以上はどうにもならない。この状態を脱出するためには幕府と戦うしかないが、そんなことはできるはずもない、勝てないのだから、諦めろ、というわけだ。この時期の幕府と大名の力関係がしのばれるエピソードといえよう。
だからといって、清正が豊臣家への忠誠心を捨てたわけでもなかった。
1611年(慶長16年)には、やはり豊臣恩顧の大名である浅野幸長(秀吉正室・おねの義弟で五奉行の筆頭であった浅野長政の子)とともに、豊臣秀頼と徳川家康の会見――いわゆる「二条城会見」実現に尽力し、両者の緊張関係を一時的ながらも緩和させることに成功している。しかしそれからわずか3カ月後、清正は急死してしまう(死因は脳溢血とも、あるいは中風の類とも)。
豊臣家が滅亡するのは、それからまた数年後、1615年(元和元年)のことである。
息子の代で崩れていく熊本藩
清正の跡を継いだのはまだ11歳の息子・虎藤だった。
彼は当時の将軍・徳川秀忠から一字を貰い受けて忠広と名乗ったが、まだ幼いので幕府によって派遣された藤堂高虎が後見人を務め、藩政は五人の家老による合議制で執り行われることになった。
しかし、秀吉の下で苦労を重ねながら戦ってきた清正ならばともかく、忠広には熊本藩54万石を維持するのはやはり無理があったらしい。その後、この藩では次々と事件が起きることになる。
1618年(元和4年)、内紛が起きた。家老の加藤美作派と、同じく家老の加藤右馬允派が主導権をめぐって対立したのである。これを「牛方馬方騒動」という。しかも、右馬允派は美作派に謀反の疑いがあるとして幕府に訴えたから、ただの内紛ではすまなくなった。背景には、豊臣政権と近く大坂の陣においても豊臣家を援助しようとしたことのある美作派と、幕府体制下に順応していこうとする右馬允派との対立があったようだ。
この騒動については秀忠による裁定が行われた。結果、美作派は大坂の陣の際に大坂側に味方しようとする動きがあったことから、右馬允派の勝訴となった。美作派は流罪となり、加藤家の政権は右馬允派が掌握することになる。
事件の遠因として、清正死後に家老たちの所領について幕府から介入があったことから不満が醸成されたという説があり、だとするならば外様大名にプレッシャーを与えたい幕府側の意図があったかもしれない。
加藤家はなぜ改易となったのか? ①表向きの理由
牛方馬方騒動の時、忠広は「事件に直接的な関係がなかった」、「まだ幼く、責任能力がない」ということで処罰されなかった。しかし、その後も藩内は勢力争いで動揺が続いた。また、清正はキリシタンに対して激しい弾圧を加え、宣教師が「その死によって肥後に平和を与えた」とか「残虐な仇敵」といった意味の言葉で表現するほどであったので、彼の死を受けてキリシタンたちによる一揆も始まったため、領内の情勢は非常に不安定になってしまったのである。
こうした情勢の中、ついに幕府は加藤家を排除し、別の大名を肥後に入れようと考えるようになった。加藤家が内紛によって弱体化したのもそうだが、南の薩摩国に存在する島津家――西軍に参加したにもかかわらず、その強さを幕府もはばかつて改易・減封処分をできなかった大大名――への抑えの役目を果たせない、と感じた部分も大きかったのだろう。
そして1632年(寛永9年)、忠広はついに肥後一国を取り上げられてしまう。理由はいくつも語られているので、主なものを紹介しよう。
ひとつは、当時、江戸で生まれた子どもは幕府の許可を得てから国に帰さなければならなかったが、忠広がその許可を得ずに無断で母子を帰国させてしまったので、それが問題視されたのだ、というもの。
また、江戸にいた忠広の息子・光正が家臣を脅かすために出陣の真似事をしたといい、この家臣が幕府に馬鹿正直に報告をしたので、これが謀反の疑いをかけられたのだ、というものもある。
加藤家はなぜ改易となったのか? ②真相?
そして、最も興味深いのが、怪文書にまつわるものだ。
時の老中・土井利勝の名前で「3代将軍・徳川家光に代わってその弟の徳川忠長を擁立しよう」という手紙が諸大名の江戸屋敷に送られたのだが、ほとんどの大名たちが驚いて幕府に申し出たのに、忠長自身と加藤家だけはこれを提出しなかった。これが問題になったのだ。
もともと家光と忠長は仲が悪く、忠長が謀反をして将軍の座を狙うということは十分にあり得た(少なくとも、人々がそれを信じる素地はあった)。しかし、利勝本人は「私はそんな(手紙を出す)ことをしていない」と言い出す。では、黒幕は誰か――そこで「加藤家が怪しい」ということになった。手紙を幕府に提出しなかったこともそうだし、以前から忠長と親しかったのもマイナスになった。
しかし、この時に忠広は江戸屋敷にいなかったのである。
加藤家の人々および息子の光正が手紙を提出しなかったのは、彼らは前述した事件を起こすような性根だったので、本気扱いせずに笑って済ませた、とされる(もしそうでなくても、当主がいない状況では下手に動けなかっただろう)。
どう考えてもこれを理由に謀反扱いされるのは理屈が合わないのだが、幕府はこの疑いのままに加藤家を改易としてしまった。利勝をはじめとする幕閣の面々が忠広を罠にはめ、かつ親・忠長派にプレッシャーを与えようとしたのでは、と見られる所以である。
息子の光正は翌年(あるいは、移送される途中で舌を噛んで死んだとも)に死に、忠広は庄内藩預かりとなって、1653年(承応2年)に死去。大名としての加藤家は清正と忠広の2代で断絶してしまったのだ。
ただ、忠広の子孫自体は生き残った、という話がある。庄内の地で女性との間に一男一女をもうけ、幕府の目から隠すために死んだことにし、百姓として生き残らせたのである。これもまた、ひとつの「再興」の形とはいえないだろうか。