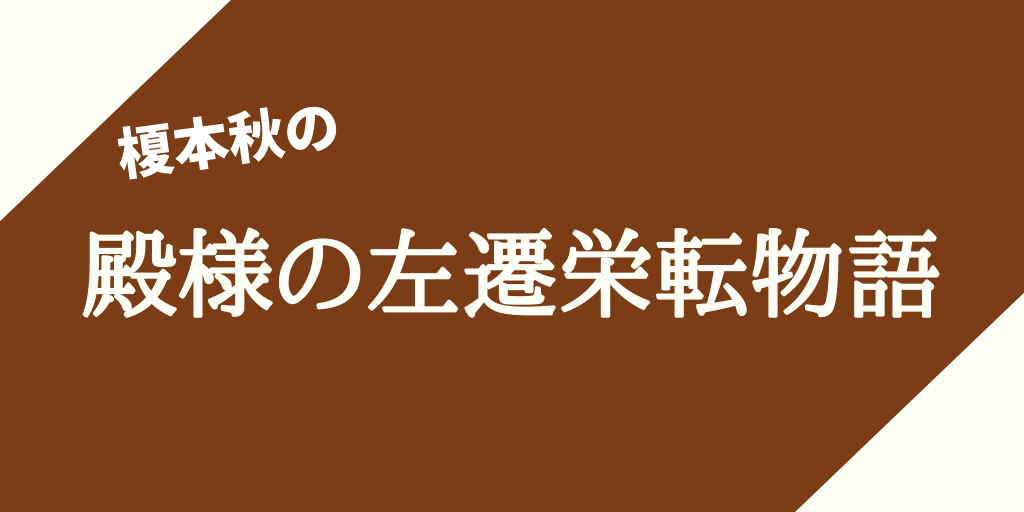
田沼の大出世
10代将軍・徳川家治の治世下においては、田沼意次(たぬま おきつぐ)という人物が権勢を振るった。
彼が活躍した時期は通称「田沼時代」と呼ばれ、重商主義的政策が推し進められて経済的に発展したが、その一方で賄賂・汚職が横行したと非難されることも多い。
意次は家治の父である家重の小姓から出発した人なので厳密には本章の対象から外れる。
しかし、父の意行はもともと和歌山藩士のそれも足軽だったのが、8代将軍・吉宗に青年時代から小姓として近侍し、彼が徳川本家を相続した際にそれに従って江戸に移り、直臣となった人物である。つまり、家系としては古くからの譜代家臣ではなく新参者であるということで、ここで紹介したい。
家重時代の政治を主導したのは老中の松平武元(まつだいら たけちか)および側用人の大岡忠光(おおおか ただみつ、言葉が不自由だった家重と意思疎通ができたことから大出世を遂げた。低い身分からの出世という意味で、意次の出世は彼の躍進の延長線上といえる)だったが、意次もまた小姓から御側御用取次に昇進し、600石取りの小身旗本だったのが1万石の大名になっている。家重も彼を「またうど(全人=完全なる人、の意)」と呼び、跡継ぎである家治にも「意次に従うように」と伝えたとされるから、よほど信頼されていたのだろう。
1760年(宝暦10年)、家重に代わって家治が10代将軍の座につくと、しばらくは武元が実権を握ったが、やがて「田沼時代」が始まる。
意次は役職としては側用人と老中を兼務し、所領はたびたび繰り返された加増によって遠江国相良藩5万7千石にまでなった。
老中として表向きの幕府最高役職を得るとともに、側用人として将軍の側近でもあり続けるというのは空前絶後のことであり、この一事をとっても彼の権勢が推し量れるというものであろう。
意次は株仲間(商工業者による同業者組合)を公認し、専売制を確立し、新貨幣を鋳造し、鉱山や新田の開発を進め――と、とにかく積極的な経済改革を進めた。
これによって経済活動は活発になったが、一方で貧富の格差が広がり賄賂が横行するという問題点もあって、また同時期に頻発した天変地異が重なるなどの悪条件もあり、一般的にはあまり高く評価されていないのもまた事実である。
意次の意外な素顔は
意次は個人としても才覚にあふれた人物で、「はつめいの人」と呼ばれた。
「はつめい」とは賢いことの意である。経済活動や金儲けになんとはなくマイナスなイメージを持ってしまう価値観は現代の私たちもそうだが、この時代の武士たちには特に「金銭アレルギー」のようなものがあった。意次はこれに真っ向から歯向かう革新的な価値観の持ち主であり、金銭をきちんと管理できないものは武士ではない、とさえ考えていたという。
確かに、当時の武士は職業的軍人というよりは(もちろん、軍人だって金勘定は必要だが)公務員であり官僚という性質のほうが強かったのだが、金銭の管理能力は絶対に必要だ――と今の私たちは思えるが、やはり保守的な武士からは激烈な反発を食らったに違いない。
しかし、意次本人の素顔は、このような「出世人」のそれとはちょっと違うところもあったようだ。すなわち、親しみやすくて腰が低く、人の心を読むことがうまく、また末端の家臣にまで親しく声をかけるような人物だった、というのである。
これは前述の忠光などとも共通する特徴で、新参者の出世人としてどうにか周囲との摩擦を減らそうという意図があったのではないか、と考えられる。また、「そげもの(変人)」として見られることを嫌い、世間並みでいるように心がけて、子孫にもそのような言葉を残した、ともいい、これなども同じような意図に基づくのではないだろうか。
それでも、このような「成り上がり者」に対して、本来幕政を独占してきた名門譜代大名の保守派たちが黙っていられるはずもない。しかし、意次には将軍の絶対的な信頼があり、また老中や側用人、親藩大名といった有力な家から息子の嫁をとったり、娘を嫁入りさせたり、息子を養子に送り込んだりといった形で縁戚関係を結び、人脈を形成することで権勢を維持していたようだ。
この辺、戦国時代に「足軽から関白」という日本史上に残る大出世を遂げた豊臣秀吉が「人たらしの達人」と呼ばれ、さまざまな物語において人当たりがよくて付き合いのうまい好人物として描かれているのと似ているようで、なかなか面白い。
やはり、異例な大出世を遂げる人間はただ才走っているような人物ではなく、人付き合いのうまい、現代風にいえば「コミュ力のある」人物でなければならない、ということなのだろう。