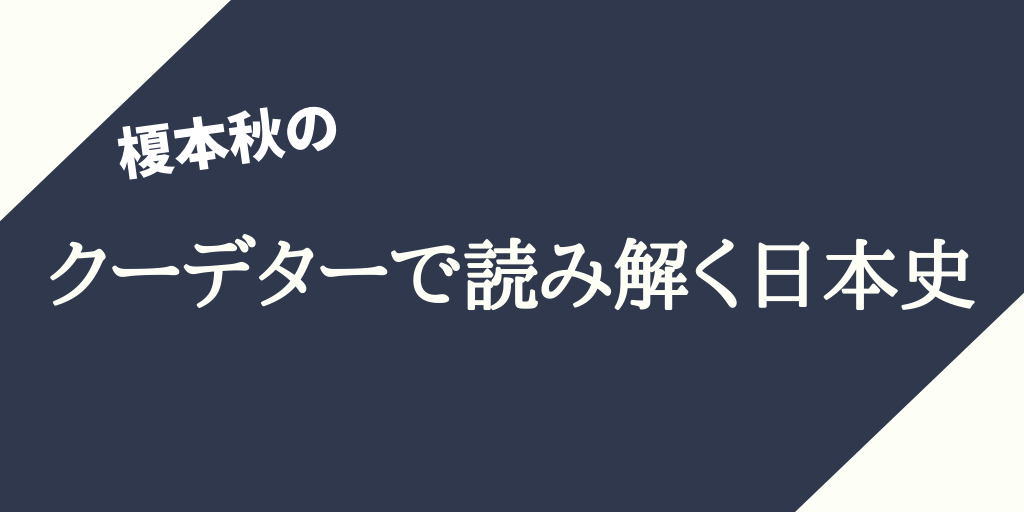
1600年(慶長5年) ○徳川家康 ×石田三成
1598年(慶長3年)、豊臣秀吉が亡くなった。
彼は天下統一に成功したが、一方で朝鮮出兵を二度にわたって行うも失敗し、一度は後継者に選んだ甥の豊臣秀次を実子・豊臣秀頼の誕生後に失脚させて殺すなど、晩年には失政が目立ったのも事実だ。
そんな彼は死に際して豊臣政権の要である五大老(徳川家康・前田利家・毛利輝元・宇喜多秀家・上杉景勝)と五奉行(石田三成、前田玄以、浅野長政、増田長盛、長束正家)に誓詞(せいし=誓約の書類)を提出させ、まだ幼少の息子・秀頼への忠誠を誓わせた。
ところが、秀吉が死ぬと早速、五大老の筆頭で豊臣政権における最大の大名であった徳川家康が独自の行動を始める。
誓詞の中で禁止されていた大名間での婚約を進め、勢力拡大に努めたのだ。
このルール違反に対して、ほかの五大老と五奉行は家康に追及を行ったが、この時は大事には至らなかった。秀頼の後見人である利家が家康と和解したからである。
その利家が病死したことにより事態は混迷の度を増す。
というのも、豊臣政権内部ではかねてから石田三成を代表とする文治派(ぶんちは)と加藤清正・福島正則ら武功派(ぶこうは=武断派)が対立しており、これを利家が押しとどめていたのだが、彼がいなくなったせいで武功派七将が三成を襲撃したのである。
この時三成は家康の屋敷に逃げ込んで難を逃れたが、その代わりに政権の中枢を離れて謹慎することを余儀なくされてしまう。
その後、家康は豊臣政権の本拠地である大坂城の西の丸に移住し、天守閣を築造した。このことは「家康は秀頼と匹敵する力を持つ存在だ」と周囲に知らしめる効果があった。
しかし、家康が真に自らの天下取りを行うためには、武力によって対立する勢力を打破する必要があった。
そのために最初は前田氏に謀反の疑いをかけ、これが失敗すると今度は上杉氏をそのターゲットとした。これに対して上杉景勝は強硬的な姿勢で望んだため、1600年(慶長5年)、家康率いる軍勢が会津の上杉氏を討伐することになった。
このことは謹慎中の石田三成にもチャンスとして捉えられた。彼としても、家康は合戦で倒さなければならない相手だったのである。
三成は中国の大大名・毛利輝元を総大将として、家康不在の近畿で挙兵したのである。「三成挙兵」の報を聞いた家康は会津行きを中止し、態勢を整えて今度は西へ向かって進軍した。
家康率いる東軍と三成率いる西軍が激突したのは美濃国関ヶ原の地であった。
この時、西軍は兵力で勝り、かつ戦場においても盆地の東軍を周囲の山に登って取り囲む必勝の陣形を組んだ。にもかかわらず、勝利したのは東軍であった。西軍側の小早川秀秋が裏切り、また吉川広家ら毛利軍(輝元は大坂城にいた)が戦いに参加しなかったからだ。
家康と三成、その勝敗を分けたのは何だったのか。
家康は戦いに先立って諸大名に数多くの書状を出し、恩賞を餌に味方へ引き入れた。合戦での裏切りも、こうした事前工作の賜物である。
対して三成が出した手紙は分かっているだけで数通だという。古代中国の兵法書『孫子』は戦争は戦う前に結果が見えるものだとし、事前準備の重要性を説いているが、関ヶ原の戦いはまさにそのとおりの結果に終わったといえる。
ただその一方で秀秋らが本当に裏切るかどうかは誰にも分からず、後に家康が勝敗は「時の運」と語ったように薄氷の勝利という部分があったのも見落としてはならないだろう。
戦後、家康は恩賞と処罰の名目で全国の諸大名を自分の思い通りの配置に置き換え、その力を大いに増した。さらに1603年(慶長8年)には征夷大将軍となって江戸幕府を開き、天下をほぼその手中に収めた。
しかし、この時点で豊臣秀頼がまだ健在だったのも事実である。所領だけを見れば65万石の一大名であっても、「豊臣政権の継承者」という権威は小さくなく、また秀吉が残した天下の名城・大坂城と莫大な遺産、加藤清正や福島正則といった東軍方についたおかげで生き残った豊臣恩顧の大名の存在も家康にとっては脅威であった。
家康としては幕府安定のためにどうあっても豊臣氏を滅ぼさねばならず、それが二度にわたる大坂の陣として結実するのである。