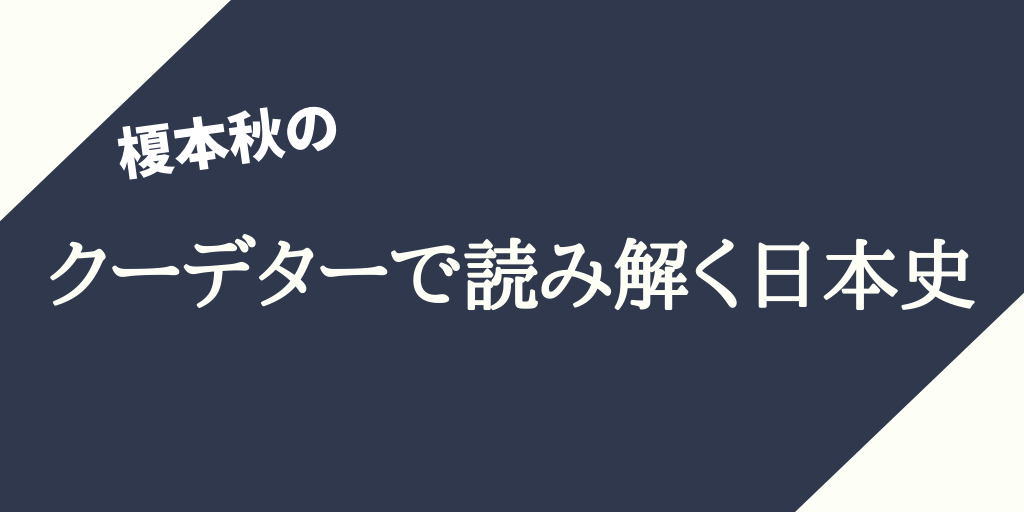
740年(天平12年) ○橘諸兄 ×藤原広嗣
長屋王の変以後、国政の中心にいたのは藤原四兄弟をはじめとする藤原氏であった。
ところが737年(天平9年)、彼らは天然痘の流行によって相次いで倒れてしまう。中心人物を失った藤原氏の勢力は一時後退し、新たな権力者の登場とそれに反発する政変を呼び込むことになった。
四兄弟死後の朝廷で力を振るったのは、光明皇后の異父兄で皇族出身の橘諸兄(たちばな の もろえ)だ。右大臣となった彼を、僧の玄昉(げんぼう)と学者の吉備真備(きびのまきび)ら、遣唐使として大陸の最新知識を吸収してきた二人が支えるのが、この時期の政権運営の形であった。
これに待ったをかけようとしたのが、藤原不比等(ふじわら の ふひと)の孫で宇合(うまかい)の長男、広嗣(ひろつぐ)であった。諸兄の躍進を見るに、藤原一族の権勢が危ない、と考えたのだろう。
740年(天平12年)の8月下旬ごろ、諸兄を支える真備と玄昉を排除するようにと書いた文書を聖武天皇に送り、返事も待たずに挙兵した。この事態に聖武天皇は都である平城京から出て、しばらく放浪をすることになってしまう。
しかし、その短絡的な行動には藤原氏内部でも批判が強かったのか、同調者は現れなかった。
そもそも、性格のせいか広嗣は藤原氏の中でも孤立しがちな人物であったようだ。元は一族の中でも期待を寄せられていて、一時は大和の知事的立場である大養徳守(やまとのかみ)に任命されていた。ところが、親族の誰かを讒言したとして九州を統括する大宰府のナンバー2である大宰少弐(だざいのしょうに)に左遷される、という経歴の持ち主だったわけだ。その大宰府で起こしたのがこの一件である。
このような事情から、九州で挙兵した彼に味方したのは弟の綱手(つなて)くらいだった。広嗣方と政府方は同年の10月に九州で激突したが、政府方の軍略により広嗣方は敗北。広嗣兄弟は海をわたって新羅に逃亡しようとしたようだが、捕まって処刑されてしまった。
こうして乱は鎮圧され、橘諸兄政権は存続することになったが、乱の余波は消えなかった。聖武天皇が平城京から出たまま、なんと6年も別の都に転々としていたのである。社会情勢が不安定な状態はしばらく続いた。
このような社会不安を抑えるために聖武天皇がすがったのは神仏の助けであった。
仏教を深く信仰し、仏の力によって国を守る――いわゆる「鎮護国家(ちんごこっか)思想」に基づいて国を守ろうとしたのである。全国に国分寺・国分尼寺を建てたのも、また有名な東大寺の大仏建設に着手したのもこの頃のことだ。
つまり、あの大仏は藤原広嗣の乱の影響によって作られたもの、ということもできるわけだ。