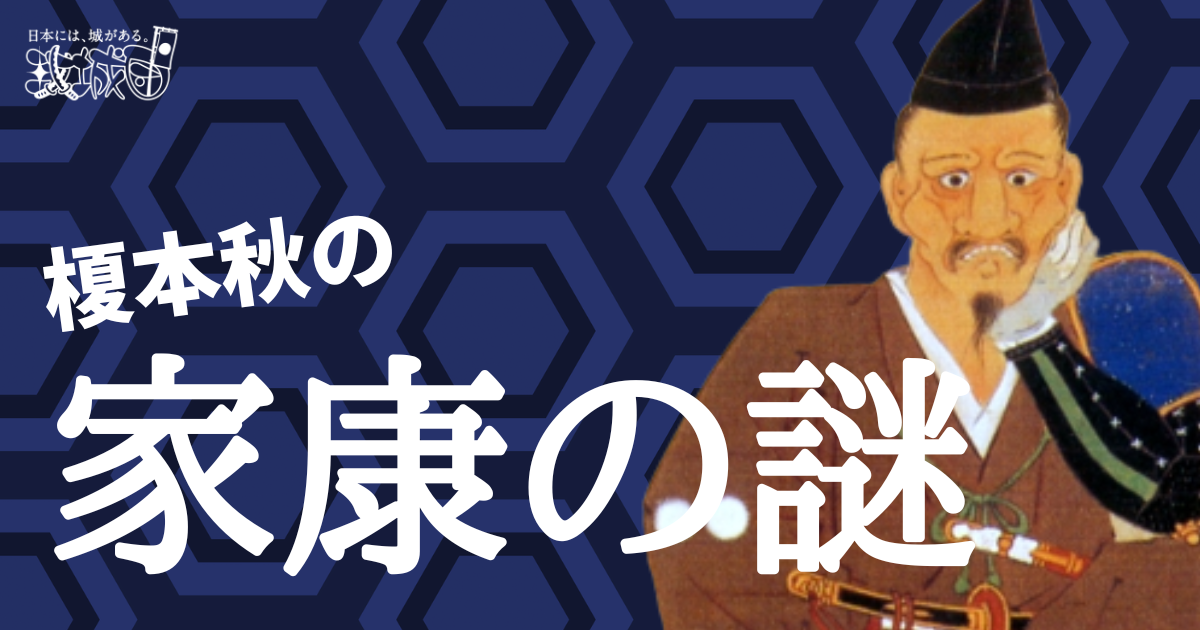
徳川家康の父は松平家の当主・松平広忠である。
ただ、彼の生涯について語るにあたっては、その父(つまり家康の祖父)・清康について語らないわけにはいかない。清康の行動とその死が広忠の人生に与えた影響は非常に大きいからだ。
清康はもともと三河の安城城を拠点にしていたが、同族の岡崎松平氏を攻めて岡崎城を奪い、ここを拠点とした。
以来、合戦を繰り返して勢力を拡大し、もともとの西三河だけでなく東三河、さらには尾張にまで進出。織田信秀(信長の父)とも戦っている。
ところが、清康はその戦いの中で突如として死んでしまう。尾張・守山城を攻めている最中、家臣・阿部弥七郎(正豊)に殺されてしまったのだ。これを「守山崩れ」と呼ぶ。
弥七郎が突然主君を殺したのは、陣中で馬が逃げる事件があり、その騒ぎを「父が処刑される!」と勘違いしたのが原因であったという。
なお、この事件の背景には、清安と松平の家督を争っている桜井松平氏の松平信定(清康の叔父)の陰謀があったという説もある。
そもそもこの両者の争いは深刻で、清康が拡大行動を繰り返したのは、桜井松平氏との争いを外へ転嫁するという事情もあったともいう。信定は信秀と繋がりがあり、清康を守山に誘い込んで挟み撃ちにするはずだった、というのだ(殺害事件自体は偶発的な事故とも)。実際、信定はこの頃まだ10歳だった広忠を岡崎城から追い出してしまっている。
さて、ここからが広忠の物語だ。
岡崎城を追われた彼は伊勢・遠江をあちこち移動した末、親族関係にある吉良や、今川の支援によってついに岡崎城を奪い返すに至ったのである。
このような過程を辿った広忠だから、戦国武将としても独立したとは言い切れず、清康時代の勢力も回復しなかったようだ。
結果、今川氏支配下の武将として東へ勢力を拡大する織田信秀と戦うことになる。もともとの居城である安城城を奪われたり、松平一族に裏切られる苦しみにも遭った。近年の研究で岡崎城を奪われていた時期もあるらしいことは以前にも紹介した通りだ。
それでも(今川の支配下にありながらも)松平氏を取り巻く状況が好転する中で1549年(天文18年)、広忠は父よりさらに若い24歳で死んでしまう。その死に方は父と同じ、家臣(織田方の刺客・岩松八弥)による殺害であった(病死説もあり)。
このように、祖父・父ともに若くして家臣に殺されるという非常に不安定な立場で、家康は松平氏の当主にならなければいけなかったのである。