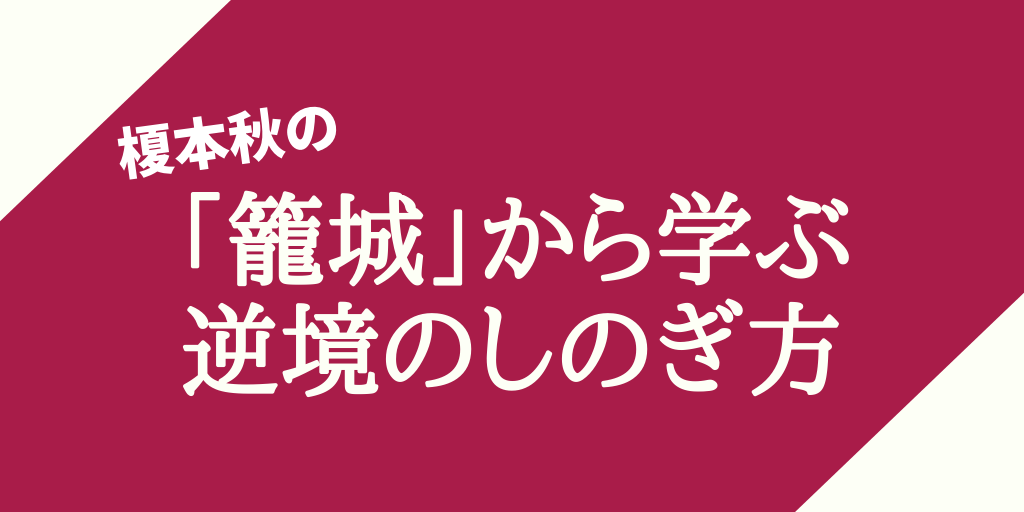
多くの場合、戦いの趨勢を決めるのは「数」だ。敵より多くの味方がいれば、有利に決まっている。
しかし、必ずしも兵士の数だけではなく、武器や兵器の数、あるいは食糧や弾薬の数が勝敗を決めることも多い。あるいは、地形や状況が数を補ってしまうことも少なくない――本書がメインのテーマとして紹介する「城」はまさにその代表例であろう。
武将の気迫やその場の勢いが、不利な状況をひっくり返してしまうケースというのも、またあるのだ。「瓶割り」の名で知られる近江の長光寺城(滋賀県近江八幡市)をめぐる戦いもまた、そんなケースのひとつである。
長光寺城は古くよりあった城で、1468年(応仁2年)の佐々木氏の内乱で使われた、という記録が残っている。
戦国時代には六角氏の勢力下にあったようだが、1568年(永禄11年)に織田信長が六角氏を蹴散らして上洛したことで、長光寺城を含む琵琶湖の南岸地域は織田氏の支配下に入っている。
長光寺城が歴史に登場するのはそれからしばらく後、信長が同盟相手であった浅井長政と決別して近江の支配権を失いかけていたころの話だ。
本拠地の岐阜城から琵琶湖を南に迂回して京都につながるルート(上洛のときに通った道でもある)を確保しなければならなかった信長は、1570年(元亀元年)にこの地域の幾つかの城に武将を配置した。そのうちのひとり、重臣の柴田勝家が入ったのが長光寺城だった、というわけだ。古い城であったから、勝家はこの城を修復しなければならなかったようだ。
その年のうちに、長光寺城は大きな戦いの場となった。
信長に敗れて領地を追われていた六角氏が、朝倉・浅井氏らと手を組んで南近江奪還のために動き出したのである。その標的になったのが、勝家の守る長光寺城であったわけだ。籠城側は攻城側に対して明らかに小勢で、すぐに本丸だけが孤立する状況になったが、勝家の活躍もあって、なかなか落ちなかった。
もともと勝家は織田家臣団の中でも武勇で知られた武将であり、「かかれ柴田」などという通称も持っていた。「かかれえ、かかれえ」と攻め立てるのが得意だったからこの名がついたらしく、まさに猛将と呼ぶのが相応しい。
このままでは埒が明かない、と見たのだろう。六角氏側は長囲――それも、渇き攻めに出た。この城の水源を断ち、籠城側を水不足に追い込んだのである。どうも、長光寺城は城内に井戸がなく、城外から水路の類を利用して水を引き込んでいたようで、そこを押さえられてしまったらしい。
城というものの性質からしてそんなに簡単に水源を断たれては困るのだが、もともとこの地域が六角氏の勢力範囲だったことから、領民たちの協力を得てこの作戦は成功した、というわけだ。たちまち城内の水は尽き、残されたのはたった三つの水瓶だけとなった。
そのまま立て籠もり続けたら、籠城側は戦う力をすべて失って降伏するしかなかっただろう。だが、ここで勝家が気迫を見せる。
「このまま立て籠もって死を待つのは無意味だ、それならば不利であっても今のうちに一戦を挑めば勝機はある!」と考えたのだろう。兵を集めて水瓶の水をすべて飲ませてしまい、全軍の意識を統一した上で、決死の戦いを挑んだのである。特に出陣に際しては、自ら空になった水瓶を叩き割り、「蓄えはこれまでだ」と言い切ったとされる。
これこそまさに、背水の陣。勝家の気迫が喉の渇きに苦しめられていた兵たちに乗り移った。
その勢いのままに突撃は成功し、織田軍は大勝。攻め手はバラバラになって逃げ散るしかなかった。以後、勝家はこの際の剛勇を称して「瓶割柴田」の異名を奉られることになった、という。