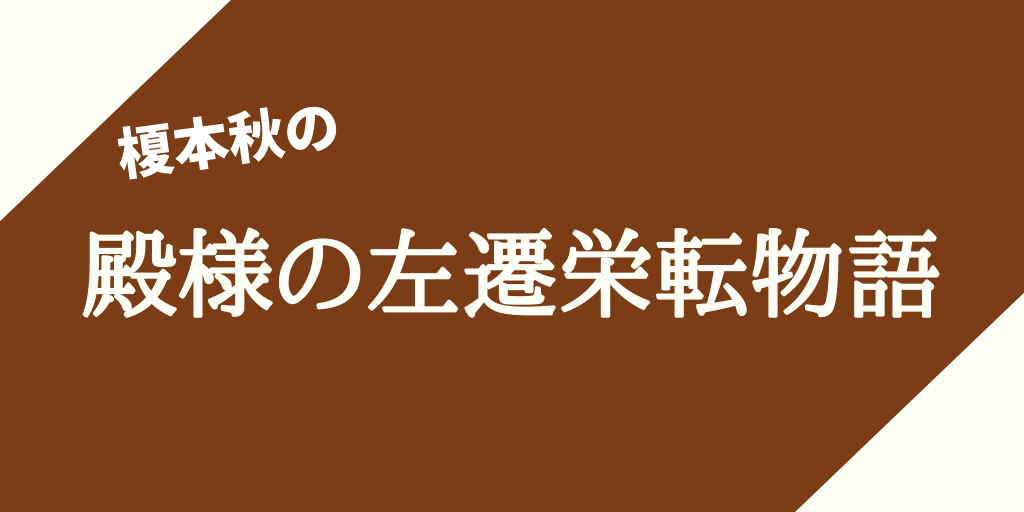
秀吉の同僚だった父を失い
立花宗茂と同じく秀忠の御伽衆に選ばれた武将の中に、丹羽長重という人物がいる。彼もまた関ヶ原の戦いで改易され、その後再興を遂げた大名だ。彼の生涯はまさに苦難の連続であった。
長重の父・丹羽長秀は織田信長に仕え、織田家臣団の中でも目立って活躍したうちのひとりだ。その血筋は鎌倉時代頃に関東で大きな勢力を誇った武蔵七党のひとつ、「児玉党」にさかのぼる。
長秀は、通称の五郎左衛門から「米五郎左」(米は地味だが欠かせないもの=長秀もまた合戦で欠かせない、の意)と称されるような才覚のある人物だった。豊臣秀吉が若い頃に名乗っていた「羽柴」という苗字は、丹羽の「羽」に同じく重臣だった柴田勝家の「柴」を組み合わせたものだという話もある。また、築城術に長けた人物でもあったようで、織田政権を象徴する存在ともいえる安土城は信長が長秀に命じて築かせたものである。
主君である信長が死ぬと、その仇を討った羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)に味方し、同僚である柴田勝家を打ち破るにあたって大きな戦功をあげた。秀吉が短期間で旧織田政権を掌握できたのには、長秀の協力が大きかったといえるだろう。
ただその一方で、長秀は信長が死んだ際には四国の長宗我部家征伐の準備中だったため近畿地方におり、光秀にも近くかつ信長の息子で旗頭になりうる信孝とも合流したのに、ついに自分が主導権をとって信長の敵討ちをしようとはしなかった、という見方もできる。ただの優柔不断か、秀吉という交渉上手に押し切られただけか、あるいは天下人にはなれない自らの器を知っていたのか。今となってはわかりようもないことだ。
なにはともあれ、長秀の協力に応える形で、秀吉は1583年(天正11年)、越前・若狭・加賀半国あわせて123万石という広大な所領を長秀に与えている。しかしそれからわずか2年後、長秀は病に倒れ、所領は息子の長重に受け継がれた。この時の長重、15歳である。
上にも下にも翻弄され続けた男
長重という男の苦難の道のりは、まさにこの瞬間から始まったといっていい。家督を継承したまさにその年のうちに、秀吉から「家臣団に秀吉に対する謀反の気配あり」と決め付けられ、所領の大半を没収されて、若狭国12万3千石へと落とされた。しかもその2年後には再び「配下の兵に軍令違反があった」とされ、加賀松任4万石にまで落とされてしまった。わずかな間の転落劇に、19歳の青年は何を思ったであろうか。
しかも、後に豊臣政権の五奉行のひとりとして活躍する長束正家をはじめ、長秀以来の重臣たちが秀吉によって独立大名に取り立てられ、その多くは丹羽家よりも石高が大きくなったのだから、これはたまらない。
この背景としては、若さゆえに家臣団を制御できない長重自身にも問題があっただろうが、それ以上に、大大名である丹羽家をたやすく潰すことによって自らの権力を誇示したい秀吉の思惑があった、と考えるのが妥当であろう。かつての上役であり、また多分に恩もある長秀は厚遇する価値はあっても、その息子はそうではない。だから、早いうちに叩き潰して将来の禍根を断ち、優秀な家臣団を自分のもとに取り込み(秀吉は譜代の家臣を持たないので、貪欲に人材を集めたとされる)、また「大大名であっても秀吉にはかなわないのだ」とアピールする「一石三鳥」を狙ったのではないか、というわけだ。
また、秀吉は長秀の死に方を「武士の本意にあらず」(『徳川実紀』)としてそのときすぐに所領を没収しようとしたものの、家康がかばいたてたのでそこでは許された……などという話もあり、そもそも丹羽家という大大名を最初から残すつもりはなかったのでは、と見ることもできるだろう。
「ボンボン大名」長重
その後、長重は1598年(慶長3年)に加増を受けて12万5千石の大名に復帰し、また「豊臣」の姓も受けている。これについては、その育ちの良さから秀吉に「御しやすい」存在として見て取られたのではないか、と考えられている。
実際、秀吉の死から始まる動乱において、長重は立ち回りの拙さを露呈してしまうことになる。関ヶ原の戦いに先立つ形で、隣接する加賀の前田利長が家康によって謀反を疑われた際には(実際には、反対派との対決を企図した家康がきっかけのためのスケープゴートとして前田家に目をつけたのだとされる)家康に味方して先鋒に立とうとした。ところが、その後、今度は会津の上杉家が標的となり、それを契機に関ヶ原の戦いが始まった際には出陣しなかったため家康の「敵」と見なされ、その後の戦いにおいて家康側についた前田家と争ったのである。
これについては、利長から「家康の味方をしよう」と呼びかけられて長重もこれに応えたものの、家臣同士のいさかいから合戦に発展してしまった――という説がある。もしそうだとするならば、かつて秀吉に所領を大きく減じられたときと同じく、家臣を統制できなかったことが長重の致命傷になってしまったことになり、「育ちのいいボンボン大名」という印象がさらに強まるのは、私だけではないだろう。
しかし、その育ちの良さが必ずしも悪いほうにばかり転がらないのが世の中の面白いところだ。長重と戦った利長は前田利家の息子であり、このふたりはそろって旧織田家臣団の重鎮の息子、いわば「ボンボン仲間」で、もともと親交も深かったらしい。
この利長が長重について「彼は徳川に歯向かったことを大いに後悔していますが、すでに関ヶ原の戦いが終わってしまったので役に立つ機会もありません。せめて罪を許してやってはくれませんか」と弁護したのである。家康はこれを聞き入れなかったが、「利長がそこまでいうのなら」と命は取らず、改易・所領没収に留めた。
長秀以来の家臣団はただでさえ代替わり直後の減封によってほとんどが離れていってしまっていたのに、これによって完全に離散してしまった。長重自身も居城である小松城を追われ、浪人となってしまう。しかし「何地なりとも立退べし」(『徳川実紀』)とはいえ、長重としてはお家再興の思いがあったらしい。そのため、長重は江戸に居住し、蟄居して再興の許しが出るのを待つことになる。
また、家康としても彼の武勇・知略、そして誠実さを評価して、このように危機に陥ったのは家臣団の姦計に惑わされたからだ、とも見ていたようだ。丹羽長秀という優れた築城技術者の息子であることから、その方面での期待もあったかもしれない。実際、のちに長重は幕府の命を受けて棚倉城の築城にかかわっている。
ただ、これは長秀時代から蓄積してきた丹羽家の財産を減らすための謀略だったのでは、という見方もあることは紹介しておこう。実際、それは幕府の常套手段だったのだから。
丹羽家は二本松藩に定着
ようやく再興の機会が訪れたのは1603年(慶長8年)のことである。この年に征夷大将軍となった家康は、前述した前田利長に加え、やはり以前から長重と親交のあった自らの嫡男・秀忠からの働きかけに応えて、彼を常陸国は古渡1万石の大名として取り立てる。この国には江戸時代を通じて基本的に親藩・譜代大名が多く配置されており、その中で丹羽家という外様大名が一時的ながらも置かれたところに、家康の長重に対する評価を垣間見る向きもある。
その後の長重は大坂の陣で活躍し、陸奥国は棚倉5万石、さらに陸奥国白河10万石余ヘとたびたび加増・転封を受けた。こうして加増を受ける中で、長重はかつて離散した家臣団を呼び戻した、とされる。
ちなみに、棚倉・白河両藩の藩主は丹羽家の後はずっと譜代・親藩大名しか入っていない。この点にも、丹羽家への(及び、丹羽の前に棚倉藩主だった立花家への)幕府の姿勢が見えてくる。
丹羽家は長重の子・光重の代に陸奥国二本松へと移され、この地で幕末の動乱を迎えている。幕末の二本松藩といえば戊辰戦争において少年ばかりの部隊が玉砕を遂げた「二本松少年隊」の一件が有名だが、そこに長重の立ち回りの拙さ、一本気な気質を見るのは、考えすぎだろうか。