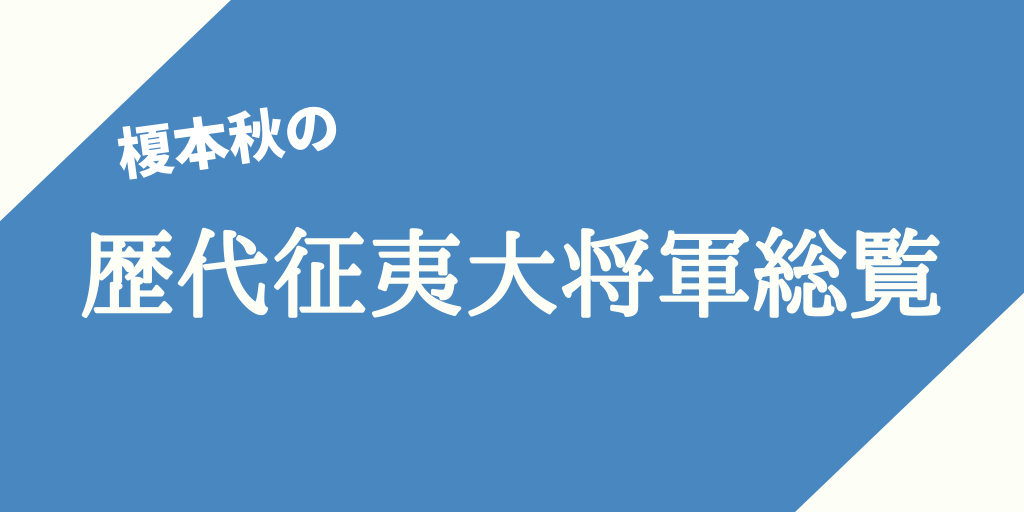
本来の征伐対象であった蝦夷が服属し、平将門・藤原純友も討ち果たされた後、「征夷大将軍」という役職もまたその姿を消し、二百数十年余り歴史の表舞台に登場することはなかった。
それが再びよみがえったのは、いわゆる源平合戦の中でのことだ。
源平合戦の渦中で
天皇と公家を中心とする政治権力が揺らぎ、ともに天皇家から分かれた血筋であるふたつの武家――源氏(清和源氏)と平氏(桓武平氏)を中心に諸勢力が激しく争うことになる。
朝廷内部の勢力争いである「保元の乱」「平治の乱」に勝利した平清盛は京に自らの一族を中心とした平氏政権を確立し、「平氏にあらずんば人にあらず」という『平家物語』のあまりにも有名な言葉に代表される平氏の全盛期を迎えた。
清盛の死の前後から平氏政権は衰亡の度合いを強め、一方で先の争乱に敗れた源氏や、清盛によって封じ込められていた後白河法皇一派が活発に活動するようになる。その中には、のちに鎌倉幕府を作り上げることになる源頼朝がいた。
しかし、この戦いは「源平合戦」という言葉からイメージされるような単純な構造でなかったのも事実である。各地では源氏と必ずしも関係のない在地武士が反乱を繰り広げて平氏政権を苦しめたし、源頼朝の妻・北条政子の実家で頼朝を強力にバックアップした北条氏の本姓は平、すなわち平氏の一族なのだ。
もちろん、源氏も一枚岩ではなかった。
頼朝と同時期に挙兵し、先んじて京へ進軍して平氏政権を追い落とした源義仲(木曾義仲)は、西に逃れた平氏だけでなく、東で様子見を続ける頼朝とも対立し、その動きに備えなければならなかった。
そんな義仲が望んで復活させた役職こそが「征東大将軍(征夷大将軍というのは誤りであると近年考えられるようになっているが、本書では義仲も将軍の一人と数える)」だった。これは東にいる敵、すなわち頼朝を討つという意思表示であり、また「武士のリーダー」としての将軍を成立せしめたもの、と考えていいだろう。
古代の将軍の項で紹介したように、将軍とは節刀を与えられて天皇の代理人となる存在であったから、武士が新たな政権を――武家政権を作り上げるにあたって、適切な大義名分であったわけだ。
義仲自身はまもなく倒れたため、このときの将軍就任そのものは情勢へ大きな影響を与えなかったようだが、このことが頼朝が征夷大将軍を名乗るのに少なからず影響を与えたはずだ。
平氏は滅び、朝廷は封じられ、武家政権が立つ
頼朝の命を受けた弟・源義経が京を占領した義仲を倒し、西で態勢を整えた平氏政権も倒し、ついに義経自身も兄との対立の末に滅びると、天下は頼朝の支配下に落ち着いた。
そんな頼朝が作り上げた組織・制度が鎌倉幕府であり、その頂点に立つ存在として就いた役職こそが「征夷大将軍」であった。これ以後、将軍とは「武士のリーダーであり、武家政権の機構である幕府で日本を統治する存在」となった。一般には頼朝が征夷大将軍に任命された1192年(建久3年)こそを鎌倉幕府成立の年とすることが多い。しかし近年では「鎌倉幕府は段階的に実行組織として成立したもので、頼朝が将軍になったのは朝廷側が名目上の承認をしたものに過ぎない」という見方が有力になっている。
そのように段階的な発展を続けていく中で、具体的にはどのタイミングで鎌倉幕府が成立したといえるのか。
これについては諸説あるが、1185年(文治元年)に朝廷が守護・地頭制度を認めた時とする説が現在は有力である。これによって武家が領主として各地を支配するシステムが成立し、日本は長い武家政権の時代に入った、と考えられるからだ。
さて、初期の鎌倉幕府は将軍・頼朝を頂点とし、彼が親政を行う形で出発した。だが、頼朝が死ぬとこの体制は速やかに変質する。父の後を継いで二代将軍となった頼家は弱冠18歳の若者に過ぎず、彼に実権を渡すのをよしとしなかった有力武士たちは合議制による政権運営を望んだのである。
その中で主導権を握ったのは頼朝の妻・政子の実家である北条氏であった。幼少のころから艱難辛苦を乗り越えてきた天才政治家・源頼朝と、若き頼家を比べるのも無理があるから、これ自体は仕方がないといえるだろう。
しかし、頼家は北条氏との確執の末に死へ追い込まれ、後を継いだ弟の実朝は実権を得られないまま、暗殺されてしまった。
将軍職を継承するはずだった源氏の正統は、ここに絶えてしまったのである。
結果として、義仲が先駆けとなり、頼朝が制度化した「武士の頂点として、源氏の血筋が継承する将軍」という存在は、わずかな間だけ歴史に現れ、消滅してしまうこととなった。その後、鎌倉幕府の将軍を務めたのは、北条氏が代々世襲する執権に担がれて権威付けの役目を果たすに過ぎない、摂家将軍・親王将軍であった……。