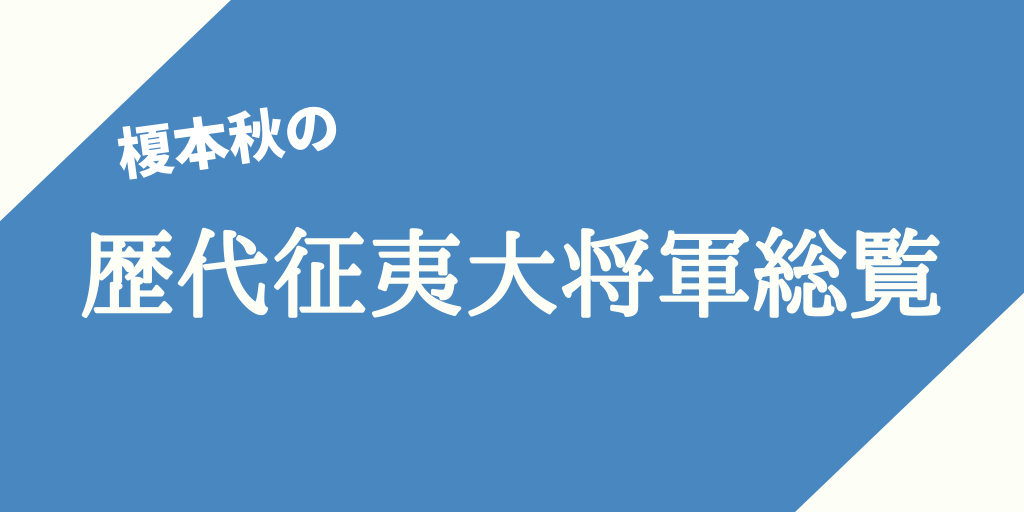
綱吉時代の払拭から始める
家宣の父は甲斐国甲府藩主で3代将軍・徳川家光の子である徳川綱重だ。
父が正室と結婚する前に生まれた子なので隠し子とされ、家老・新見(しんみ)備中守正信の子「新見左近」として育った。ところが、結局綱重と正室の間に男子は生まれず、家宣の出自が明かされて将軍家を継ぐことになった。
家宣は生真面目で礼儀正しい人であったようだ。学問に熱心で、後述する新井白石(あらい はくせき)からさまざまなことを学んだが、その際はどんなに暑くても正装で臨み、扇で扇いで涼をとろうとさえせず、蚊がやってきても無視した、という。講師に対する礼儀を守り、学問以外のことに意識を割かない、驚くほど真面目な生徒であったのだ。
また、将軍の後継者になるにあたっても、いち早く贈り物を用意しておもねってきた幕府重鎮に対して、むしろ相手を遠ざけるという断固たる姿勢を見せた。これもまた、生真面目さの表れであるといえよう。ただその一方で猿楽を好み、家臣にたしなめられるという側面もあった。
そんな家宣が1709年(宝永6年)に将軍になって真っ先に手をつけたこと、それは綱吉時代からの負の遺産というべき生類憐みの令を撤廃することだった。
綱吉は遺言として「生類憐みの令が民衆を苦しめていることはよく知っている。それでも、せめて私の死後も3年は続けてほしい」と家宣に頼んで死んでいる。しかし、家宣は民のことを最優先し、柩に「私自身はあなたの遺言を守ります。けれど、庶民のことはどうかあきらめてください」といった言葉をかけ、綱吉の葬式も挙げないうちに生類憐みの令を撤廃してしまったのである。どこまでも真面目な男だ。
このほかにも、綱吉時代に大きな権限を有していた柳沢吉保を幕政の一線から退け、また賄賂の横行をとめるための法令を整備するなど、前代の政治からの転換を次々と打ち出していく。
この時期は富士山の噴火もあり、生類憐みの令もあって多くの庶民が幕政に不満を持っていたが、新将軍の改革を多くの人々が喜んだことだろう。
側用人政治は継承する
家宣は先代の政治を何もかも否定したわけではない。むしろ、政治スタイルそのものは継承した、といっていい。
すなわち、綱吉が館林藩時代の家臣たちを幕政においても重用したように、家宣もまた甲府藩時代からの家臣を登用して自らの政治を行ったのである。さらに、側用人を置いて老中と距離をとり、自らの意思を幕政に強く反映させようとしたのも綱吉時代と同じだ。
家宣の治世下において特に重用されたのはふたり。ひとりは間部詮房(まなべ あきふさ)で、猿楽師から小姓を経て大名にまでなった人物である。仕事熱心な無私の人であり、また人柄も温厚で、大出世を遂げながらそれに溺れることもなかったという。
いまひとりが新井白石。こちらは儒学者で、頭の回転が速すぎる人物だったようだ。人々は彼のことを「鬼」と呼んで恐れ、また嫌ったと伝わる。のちに政治の一線から退いた後は執筆に没頭し、自伝『折たく柴の記』、諸藩記録『藩翰譜(はんかんふ)』、海外事情をまとめた『西洋紀聞』『采覧異言(さいらんいげん)』など多数の著作を残した。
この対照的なふたりが進めた一連の政治を「正徳の治(しょうとくのち)」と呼ぶ。先述した綱吉時代の悪影響の払拭のほか、進行していたインフレを食い止めるために純度の高い正徳金銀を発行したり、朝鮮外交における経費を削減したり、といった政策が知られている。朝鮮外交については、「日本国王」の号を使用することによって将軍の権威をさらに高めたことも見逃せない。
だからといって、家宣が何もかも彼らの言いなりになったのではない。
たとえば勘定奉行の荻原重秀(おぎわら しげひで)という人物については、白石が厳しくやめさせるよう求めたにもかかわらず、その才覚を認めてこれを拒否、長く勘定奉行として使い続けた(最終的には白石に押し切られたのだが)。優秀なブレーンを頼りにしつつも、リーダーとして自らの判断を押し通す姿が想像できるというものではないか。
このように理想的な政治を展開するかに見えた家宣時代だが、将軍就任から3年後の1712年(正徳2年)に終わりを告げてしまう。病没である。
51歳だからそこまで早い死でもないが、やはりこの年になってからの将軍就任は体に負担のかかるところも大きかったのだろうか。その遺書にも「短い時間しか将軍で居られなかったので、思うところを為せなかった」と書かれ、家宣の無念が表れている。
家宣の死後は白石・詮房のふたりが引き続き側用人として実権を掌握し、「正徳の治」を継続していくのだが、これについては次項に譲る。