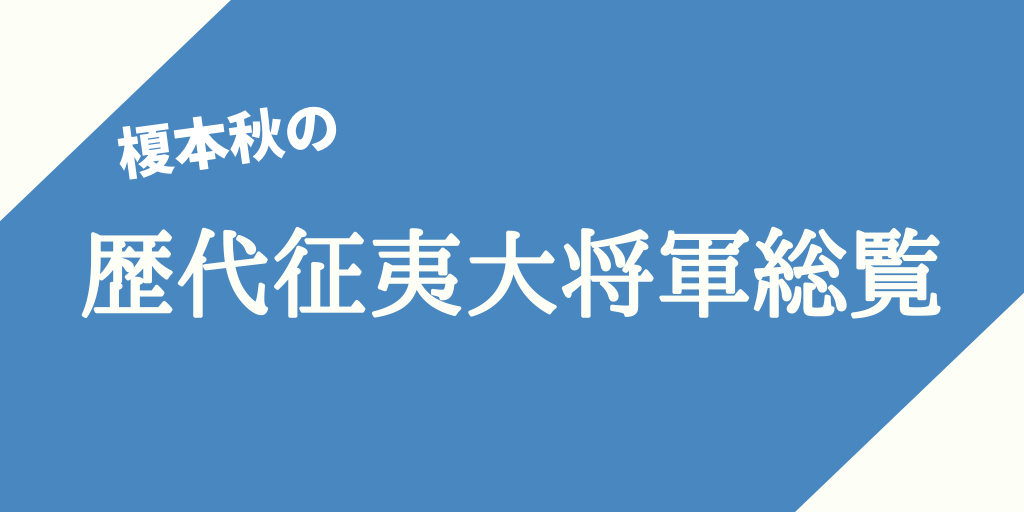
名君の子ではあったが……
家重は父・吉宗がまだ紀伊藩主だったころに生まれた子であり、1745年(延享2年)に父から将軍職を譲られた際にはもう35歳になっていた。
にもかかわらず、彼の治世の初期は吉宗が大御所として政治にかかわり、父が中風など病気によって健康を損なってからは老中・松平武元(まつだいら たけちか)や側用人・大岡忠光(おおおか ただみつ)などが中心となって幕政を取り仕切っていたという。
後期には、この次代に活躍する田沼意次(たぬま おきつぐ)も頭角を現した。
なぜそうなったかといえば、彼が大変な虚弱体質で、しかも言語が不明瞭で側近たちさえもそのほとんどが将軍の言葉をうまく聞き取れなかったからだ。
加えて、吉宗がどうにか学をつけさせようと勉強を強要したが受け入れなかったという話もあるので、彼自身の性根も将軍としての責務の方向には向いていなかったらしい。
吉宗としては長幼の序を守って長男である家重を後継者にするつもりだったのだが、一方で彼が幕府という巨大組織のリーダーに向いていないこともわかっていたろう。それに対し、次男の宗武(むねたけ)と四男の宗尹(むねただ)はそれぞれに利発だったというから、迷うこともあったらしい。吉宗の下で活躍した筆頭老中の松平乗邑(まつだいら のりさと)が宗武を擁立しようと画策した、という話まで残っている。
結局、将軍になったのは家重であり、宗武には田安家が、宗尹には一橋家が、それぞれ新しく興された。これに家重の子・重好(しげよし)が吉宗の遺言によって清水家を興し、「御三卿」が成立することになった。
言葉が不自由な将軍
家重の言語不明瞭の原因は「虚弱体質のせい」「若いうちから酒と女におぼれたせい」「幼いときの病気(脳性麻痺)のせい」などといわれている。
このことはオランダ人の残した史料にも「自分の意思を言葉で伝えられず、合図のようなもので伝えるしかなかった」といった意味の記述がなされているから、かなり有名なことだったのだろう。体の弱さについても、「寛永寺への参詣に際して何度も小便に行き、小便公方と呼ばれた」などというなんとも情けない話が残っている。
このように本人が政治にかかわることを望まなかったとしても、鎌倉幕府の時代のような完全な傀儡将軍でもなく、まったく政治から無縁というわけにもいかない。そのときに他者とコミュニケーションできない家重の代弁者となったのが、先述した側用人・大岡忠光である。
なぜかといえば、忠光ひとりだけが家重の不明瞭な言葉をしっかりと聞き取ることができ、「将軍の口」として活躍したからだ。結果、彼は小姓から2万石の大名にまで出世を遂げることになる。何度か紹介したように、側用人という役職そのものが将軍の代弁者という性質を持っているのだが、忠光はその極端な例といえるだろう。
このような状況で綱紀が保たれるはずもなく、幕政は少なからず緩んだという。そんな中、1760年(宝暦10年)に長男・家治に将軍職を譲って隠居する。家治はその理由を「父の病のため」と語っており、実際にこの翌年、家重は病没している。
竹内式部事件の意味
彼の治世下で起きた事件として、「竹内式部事件(たけのうちしきぶじけん=宝暦事件)」というものがある。京で人気を集めていた神道家の竹内式部という人物が謀反を疑われ、京都所司代によって捕らえられてしまった事件だ。
実際のところ、彼は別に幕府を倒そうと企んでいたわけではないらしい。竹内式部はあくまで天皇の偉大さを主張し、その尊さを人々に知ってもらおうと情熱を燃やしただけだった。しかし、実権を完全に奪われて名前だけの存在となっていた公家たちのプライドには響くものがあった。数十人の公家が式部の門弟となり、中には武術の訓練を始めるものまでいた。
これを危険視した他の公家たちが所司代に通報したものの、武家側としては当時このことを大きな問題とは捉えておらず、再三の要請に応えてようやく追放処分とした。
この一件は、後の幕末の動乱における尊王攘夷思想隆盛の先駆け的存在であり、またかつて江戸時代初期に朝廷と公家を政治から締め出した幕府としては、その方針を貫くために重く扱うべき問題であった。
にもかかわらず、所司代の対応がどうにも鈍く、いわば「舐められない」ための対応が甘かったことは、のちの幕末期の動乱につながる問題として覚えておくべきことだろう。