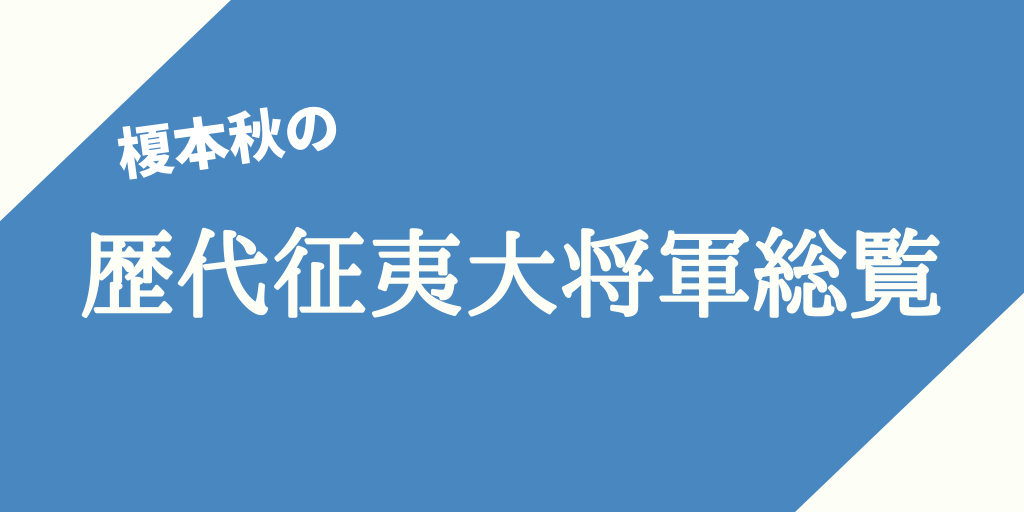
細川頼之の活躍と失脚
義満は4歳のころ、南朝軍によって京を追われた父、義詮が近江に逃れたため、播磨白旗城の赤松則祐によって養育されることとなった。
7歳になったころには京都の情勢が落ち着いたので京に戻っている。その途中、摂津の琵琶塚で宿泊した際に、その地の素晴らしい景色を気に入った義満が「この地を担いで京都に持って帰れ」と近臣たちに命じたという。まだ幼い義満の、スケールの大きさを窺うことが出来るエピソードだ。
その後、1367年(貞治6年)に父が死去したため足利氏の家督を継いだ。征夷大将軍に任じられたのは、その翌年のことだ。
1378年(永和4年)に新邸、いわゆる花の御所を室町に築いて移り住んだため、後世に室町幕府の名が定着した。
義満が将軍となった当初は、管領として細川頼之が補佐役についた。頼之はまだ幼い義満に代わり、3年の間は一切の政治を取り仕切っている。さらに、義満の養育も任されていた頼之は、彼の師となる者を慎重に選び、また内法三箇条を作成して家臣らを戒めた。名目上は補佐だったが実際には幕政の実権を握っていた頼之に対して、守護大名たちの不満は少なからず蓄積していったようだ。しかも、彼はあの手この手で守護大名たちを押さえ込もうとしていたから、なおさらだ。
それが表面化したのが、有力御家人・土岐頼康との対立だ。1368年(応安元年)、南禅寺の僧徒と叡山の僧徒が争う事件があった。この時に頼之と頼康が出兵したのだが、対策に関して両者の意見がぶつかり合い、その結果頼康が幕府を去ってしまう。
この争いについては頼康に味方する武将も多く、頼之は反感を買うことになった。それどころか、頼康が幕府を去った翌年、南朝方に攻められた御家人の救援に向かう際、頼之の提案した策を拒否する者もいたという。そのため義満は頼之に帰国するよう命令し、次の管領として越中守護の斯波義将を任命した。これが1379年(康暦元年)のことで、いわゆる「康暦の政変」である。
将軍権威確立を目指し、ときには悪辣な手も
康暦の政変後、義満はさらに守護大名を押さえ込み、自らの権限を強化するために奔走することになる。一度は失脚した頼之を呼び戻し、その養子である細川頼元を管領に据えたのもその一環である。
最初のターゲットとなったのは、康暦の政変でも対立した土岐氏である。頼康が没し、息子の康行が美濃・尾張・伊勢の守護職を継承したものの、義満はこれに介入し、尾張を取り上げて弟の満貞に与えてしまった。当然、土岐氏は内紛を起こしたので、義満は幕府軍を派遣して鎮圧。見事に弱体化させたのである。
続いてターゲットにされたのが、因幡・伯者・丹波など11ヶ国の守護を務める山名氏であった。この11という数字は全国66ヶ国の実に6分の1に達したわけで、どれだけ強大な力を誇ったか、わかっていただけるかと思う。
義満は但馬守護の山名時義が亡くなると、不遜を理由に時義の子である時熙や氏之の追討を命じた。追討を命じられたのは、時熙兄弟の伯父にあたる氏清と、従兄弟にあたる満幸であった。彼らは最初、許してくれるよう義満に嘆願したが、受け入れられずに討伐に至った。
しかし敗れた時熙兄弟が没落し、その遺領を氏清と満幸が引き継ぐことになると、彼らの勢力はますます増大してしまう。満幸にいたっては上皇の所領である出雲の横田庄を横領したり、幕府や将軍からの命令に応じなかったりと、驕りたかぶった態度が目立つようになっていった。
そのころ、時熙兄弟が密かに入京し、幕府に赦免を願い出ていた。義満はこの嘆願を受け入れて兄弟を許そうとする。しかし一方を立てれば一方が立たずとはよく言ったもので、氏清は急な義満の心変わりに不満をもった。結果、その意思表示として、1391年(明徳2年)10月に宇治の別邸で会合をするはずだったのに、中止にしてしまう。
氏清の義満に対する不満を知り、満幸は彼を謀反に誘う。さらに兄の義理にも協力を頼み、12月にはそれを実行に移す。山名氏謀反の報せを受けた幕府は、義理に思いとどまるようにと文書を送ったが、彼らは聞き入れず京都に進出してくる。義満は征討軍を結成し、両者は内野の地で激突した。その結果山名軍が敗れ、氏清は戦死。満幸と義理は敗走して行方不明となったが、満幸はその3年後に京都で討たれた。
こうして「明徳の乱」と呼ばれる山名氏との戦いは終わったが、義満は戦後、時熙と氏之にそれぞれ一国の守護を任せるのみに留め、山名氏の勢力を一気に削減した。
このように強権を振るって将軍権力の確立に努めた義満だが、それだけに「専横が過ぎた」という評価もある。すなわち、自分の好き嫌いだけで臣下の任官や叙位の決定を行い、公卿の中には義満に気に入られようとして媚を売る者が続出した、というのである。具体的な例でいえば、本来親王宣下を受ける立場になかったはずの常盤井宮満仁王が、親王になったことなどが挙げられる。この場合は、満仁王が妾の小少将という女性を義満のもとへ送り、機嫌取りを行わせたためだという。
南北朝の合一を果たす
こうして有力大名らの勢力を削っていった義満は、次に南朝との和平に乗り出す。
南朝自体はこのころまだ健在ではあったものの、征夷大将軍として信濃にいた宗良親王も、征西大将軍として九州にいた懐良親王も、それぞれ同時期に亡くなってしまっている。しかも、明徳の乱によって幕府の権威は不動のものとなり、南朝に逆転の目はなくなった。これによって、南朝の中でも幕府との和平の動きが見え始める。
こうして和平が成立し、天皇の権威を象徴する剣・鏡・玉の三種の神器が南朝から北朝へ譲り渡されることになる。1392年(明徳3年)、南朝から神器とともに出発した後亀山上皇が、後小松天皇に迎えられて入京し神器を奉った。ここに南北朝の統一が実現し、57年ぶりに皇統がひとつになったのだ。
しかし、このときの条件として持明院統と大覚寺統の「両統迭立(りょうとうてつりつ=両統から交互に皇位につくとされた皇位継承の原則)」が提唱されたにもかかわらず、義満は大覚寺統の人間を排除してしまったので、後々までその怨恨が残ることになったのもまた事実である。
南朝が消滅したことで、義満はさらにその独裁政治を強める。
2年後に将軍職を息子の義持に譲って太政大臣となったが、将軍の実権は未だ義満の手の中にあった。そもそも将軍職を譲ったのも政治から退くためではなく、出家して俗世間から離れることで、幕府にとらわれないより自由な政治を行うためだった。
義満は出家の儀式を行う際、それを法皇受戒の儀式になぞらえて行ったという。そうすることで、自らの地位を法皇と同じところまで高めようとしたのだと考えられる。この後も義満は、たびたび法皇になることを望んでいるかのような行動をとっている。
1397年(応永4年)に北山第を造営し、ここに移り住んだ。この北山第の一部が、有名な金閣寺である。義満はここを仙洞御所(上皇の御所)に似せて造ったというから、出家の時の儀式と同じく、自分を法皇になぞらえようとしたのだと思われている。
その目は海外へ
守護大名という内部の敵と、南朝という外部の敵を片付けた義満が、次に目をつけた目標。それは外国――明との国交再開であった。
日本と外国との国交は、鎌倉時代に起こった元寇以来、絶たれていた。その再開に向けて義満が動き出したのは1401年(応永8年)のことで、九州の商人・肥富と僧・祖阿を使者として明に送ったのが始まるである。翌年になって肥富らが明の使者とともに帰還したので、義満は北山第で明からの国書を受け取ったのだった。
この国書には「日本国王源道義」と記されていた。道義は義満が出家後に改めた名前であり、義満はこれに応えて「日本国王臣源」と返書している。明への従属姿勢を見せた義満に批判はあったが、義満自身は明に仕える、という意識よりはむしろ、国書にあった「日本国王」という文字通り、一国の主権者であるという意識が強かったのだろう、と考えられている。
ともあれ対明交渉は成功した。義満はこの貿易により利益を生み出すことを目的としており、実際に絶大な効果を上げた。
遣明使を遣わす際、船に甲冑や刀などの兵具を積み込み、明で民間相手に商売を行い、利益を上げたという。このような明との貿易によって上げられた利益が、この時期の幕府の大きな収入源となった。
「法皇」を目指した将軍?
こうして室町幕府の最盛期を築き上げた義満だったが、1408年(応永15年)に後小松天皇の北山第行幸があり、その翌月に息子・義嗣の元服式を終えた辺りから、体調が優れなくなった。
医師の参仕によって一時は回復に向かったものの、すぐにまた悪化し、そのまま息を引き取った。享年51。死因は咳病とされているが、流行病という説もある。
義満の死後、朝廷では彼の功績を讃えて尊号を贈ろうと話し合いが行われた。
しかし義満はすでに従一位という最高位に叙せられており、太政大臣も令制上での最高官であるため、贈るべき官位がない。あるとすれば、天皇が父を尊敬して贈る太上法皇という称号だ。義満は後小松天皇の幼いころからの養育係だったこともあり、朝廷では義満に太上法皇を宣下することが決まった。
だが彼の後を継いだ足利義持が辞退したために、結局それはかなわなかった。義満はおそらく生前から太上法皇の宣下を望んでいたと見られるが、死後の話では義持の意見を覆すことなどできなかったのである。