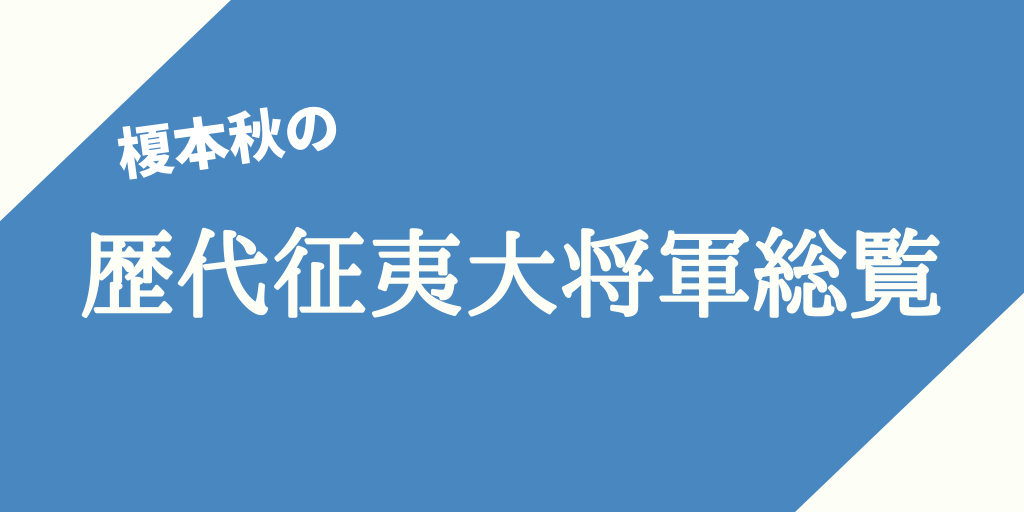
名門・足利氏の当主はなぜ討幕に加担したか?
初名は高氏(本連載では基本的に尊氏で統一する)。足利貞氏の次男として誕生。15歳のときに従五位下治部大輔に任じられて、六波羅探題北方を務めていた北条久時の娘・登子と結婚した。
尊氏が大きな動きを見せるのは1331年(元弘元年)のことである。この年、後醍醐天皇が挙兵。尊氏は幕府軍の大将として上洛、これを平定する。捕らえられた後醍醐天皇は、配流となった。
しかし天皇に味方する勢力の動きはむしろ活発になり、ついに2年後、天皇が隠岐を脱出し、伯耆の船上山にこもる。これに際して再び西上を命じられた尊氏だったが、丹波まで進んだところで北条氏討伐と源氏の再興を宣言した。そして諸国の豪族たちに密かに手紙を送り、協力を要請した。すると続々と賛同者が集まり、尊氏に味方する者の数は5万を超えたという。
さて、尊氏はなぜいきなり討幕に転じたのだろうか。
2度目の西上の折、尊氏は近江にて後醍醐天皇より味方につくようにとの命令を受けたという。しかしそれより以前に討幕の意思はあったと見られ、1度目の西上は後醍醐天皇を攻めるためではなく、討幕のための下見だったという考え方もある。
決断の理由を『太平記』は「父の喪中にもかかわらず、笠置城への出陣を命じられたこと」「自身の病気の最中に船上山への出陣を命じられたこと」としている。いわば「私怨説」だ。
一方、「置文伝説」と呼ばれる伝説をその背景として見る考え方もあり、それによると、足利家のルーツである源義家は「七代後の子孫に生まれ変わり、天下を取る」という置文を残し、しかし七代後の子孫である家時は自決、「自分の命を縮め、三代のうちに天下を取る」ともうひとつの置文を残しており、これが動機だった、というのである。
しかし、前者はあくまで私怨で、それだけで尊氏が討幕に踏み切ったとは考えにくい。後者についてはただの伝説として否定されている。
そのため、全国的に反幕の気運が高まっていたこと、北条氏の足利氏への経済的要求が高く(閑院内裏と六条八幡宮の造営に足利氏は費用をかなり負担した)、それが北条氏へ不満を抱く原因となったことなど、多様な事情があいまって決断に至った、と考えるのが妥当であろう。
ともあれ、京に進軍した尊氏は、六波羅探題を攻め滅ぼすことに成功した。翌月には後醍醐天皇が帰京し、鎮守府将軍に任命される。さらに後醍醐天皇の諱である「尊治」から一字を与えられ、ここで「尊氏」と改名した。同時期に新田義貞らが鎌倉を滅ぼし、北条高時をはじめ北条一族を自害に追いやって、幕府を滅亡させたのはすでに紹介したとおり。
尊氏と天皇のすれ違い
討幕に大きな役割を果たした尊氏だったが、建武の新政において重く扱われていなかったようだ。当初から求めていた征夷大将軍の職が与えられないどころか、そもそも新政府に役職がなく、人々は「高氏(尊氏)なし」と驚きとともにささやいた、という。
この背景には、もともと源氏の名門として声望が高く、討幕での功績も大きい尊氏に対する警戒があったのだろう。さらに彼は、天皇が戻る前から京に奉行所を設置し、天皇方についた武士たちの功績を聞いて恩賞の約束をしていた。これによって多くの武士たちは尊氏をこそ慕い、尊氏派の勢力は非常に拡大していたのである。
ただ、急進的な反尊氏派であった護良親王が、尊氏との対立の末に処罰されたことを見るに、この時点ではまだ完全に危険視されていた、というわけではないようだ。
1335年(建武2年)に「中先代の乱」が起きて、北条時行によって鎌倉を攻め落とされると、尊氏は兵を率いて討伐に向かった。この際、征夷大将軍を望んだがかなわず、かわりに征東将軍に任ぜられている。
鎌倉を平定した尊氏は、いよいよ天皇から離反する。鎌倉に拠点を構え、帰還を命じる天皇の命令も無視した。また、弟の足利直義が「新田義貞を討つから力を貸してくれ」と全国の武士たちに働きかけている。義貞は鎌倉幕府滅亡の功労者であるし、建武の新政では厚遇されていた人物であるから、これはすなわち天皇への謀反に他ならない。
ただ、尊氏自身がどこまで天皇と戦うつもりだったのか、はよくわからない部分がある。
天皇の命を受けた義貞が討伐にやってくると、一旦弟の直義に政務を譲り、鎌倉の浄光明寺という寺に閉じこもって恭順の姿勢を見せているからだ。それでも、新田軍に直義の部隊が敗れたことを聞いてようやく動き出す。
苦難を乗り越え、念願の征夷大将軍ヘ
西に向けて進んだ尊氏の軍勢は、義貞を箱根で破り、伊豆、近江と合戦を経て1336年(建武3年)に入京。京都の各地でついに天皇方とぶつかった。
ここで一度は敗れた足利軍だったが、九州に下り武将たちに参戦を募って態勢を立て直す。順当に行くならば足利氏の名声が高い関東を選ぶべきだったのだろうが、あえて九州を選んだ決断は成功し、この地で天皇方の勢力を蹴散らした尊氏は、大きく勢力を回復する。
そして、天皇方の追撃を食い止めるために山陽道や四国に配置してきた諸将らが危ういと聞くと、尊氏率いる部隊が海路から、直義率いる部隊が陸路から、再び上洛を目指したのである。
決着がついたのは、摂津国湊川での戦いだった。九州で兵力を蓄えた足利軍の兵力は圧倒的で、智略で挑もうとした天皇方を3時間に及ぶ戦いの末に、ついに破ったのである。後醍醐天皇は京都の花山院に軟禁となり、持明院統の光明天皇が新たに即位した。
しかし後醍醐天皇は花山院を脱出して大和国の吉野に逃れ、自らが天皇であることを主張してここに吉野朝廷を成立させる。この吉野朝廷を南朝、京都の朝廷を北朝として、南北朝時代が幕を開けた。
一方の尊氏は、光明天皇が即位したすぐ後に『建武式目』を制定。尊氏の施政方針を示したこの十七ヶ条の法令により、室町幕府が成立する。
1338年(暦応元年)には新田義貞を越前に討って、念願の征夷大将軍就任を果たす。さらに翌年には後醍醐天皇がこの世を去り、尊氏の前途は明るいと思われた。
弟と部下の板ばさみに
そんな尊氏を苦しめたのは、幕府内部の争いであった。尊氏の執事である高師直と、尊氏の弟・直義の対立が激しくなっていったのである。1349年(貞和5年)になるとついに、師直が直義を討つために大兵力を動員するまでに至った。
この事態に尊氏は、直義を自分の屋敷にかくまいながら師直をなだめ、両者の仲立ちをしながら和平交渉を進めさせていった。その結果、直義が師直の条件をほぼ全て承諾し、政界から退くことになる。代わりに尊氏の嫡子である義詮が政務を担当することになった。
この一連の流れに関して、尊氏は師直と密かに打ち合わせをしていたと考えられている。
もともとは、尊氏が「この世の幸福を直義に全て与えてほしい」と書いた願文を清水寺に納めるほどに、直義との兄弟仲は良かった。しかし直義と師直の勢力が対立するにつれ、尊氏と直義にも亀裂が入り始めていった。尊氏は、やがて自分の子の義詮に将軍職をゆずることも考えた上で、直義を政界から退けようとしたのでは、というわけだ。
出家した直義も、あきらめたわけではなかった。
彼は師直討伐を企てて南朝と手を結ぶために動いていたのである。しかも、尊氏によって九州に追いやられていた直義の養子・直冬(尊氏の実子)がその勢力を伸ばし、中国地方まで迫っていた。これを受けて、尊氏が直冬征伐のために京都を出陣すると、その留守を狙って直義が進撃してきたのである。義詮が防衛にあたったものの防ぎきれず、丹波へ敗走した。
不利を悟った尊氏は弟と和睦を結んだものの、直義は長年の敵である高師直を許すことはできなかったのか、師直の一族は直義方の兵らによって殺害された。この処置に尊氏は怒り、尊氏・義詮派と直義・直冬派との全面対立となった。「観応の擾乱」と呼ばれるこの乱により、十数年にわたって全国的に動乱が続くこととなる。
1352年(文和元年)には直義を破って降伏させ、ともに鎌倉に入ったが、そのすぐ後に直義は急死した。死因は病死と公表されたが、実は尊氏が毒殺したのだという噂が当時から流れていたといい、おそらくはそれが真実であろう。今後また敵対勢力となる可能性を憂いて殺したと考えられる。
いまだ南北朝の動乱は終わらず……
1355年(文和4年)に入っても、東国を押さえた幕府、中国の直冬、九州を席巻する懐良親王の南朝勢力による、ある種の天下三分状態になっていた。
中国勢とともに直冬が京都に向かっているのを前年のうちに知っていた尊氏は、あらかじめ京都を出て播磨の方へ逃れていた。合わせて義詮も近江に向かう。そして直冬らが京都に入ると、尊氏と義詮は播磨と近江の両方から敵を挟み撃ちしたのだった。
ここで直冬を打ち破ったことで足利氏内部の混乱は終わったものの、問題は残っていた。
懐良親王がいよいよ勢力を高め、九州の北朝方は薩摩の島津氏くらい、という状況になっていたのだ。
1358年(延文3年)、尊氏は九州に向かうことを決意。しかし尊氏の体調がすぐれず、遠征は中止となった。やがて背中に腫れ物ができ、それ以降尊氏の健康状態は悪化。そのまま回復することなく、息を引き取ったのだった。
その生涯を追いかけてみると、尊氏という人は幾度も厳しい選択を強いられ、それに的確な決断を下すことで大きな業績を残した、という印象がある。夢窓疎石が「どんな時でも、工夫を凝らすことを怠らなかった」と評したことも、その印象を強めている。
ただその一方で、幕府創設に成功した年の願文に「この世は夢のようなもの」「遁世してしまいたい」などと書いてしまうような、不安と無常の気持ちを抱いていたことも、また事実である。
動乱の時代に生まれ、次々と移り変わる情勢に翻弄されながら、必死に生き抜こうとしていた当たり前の人間。それが尊氏だったのだろうか。