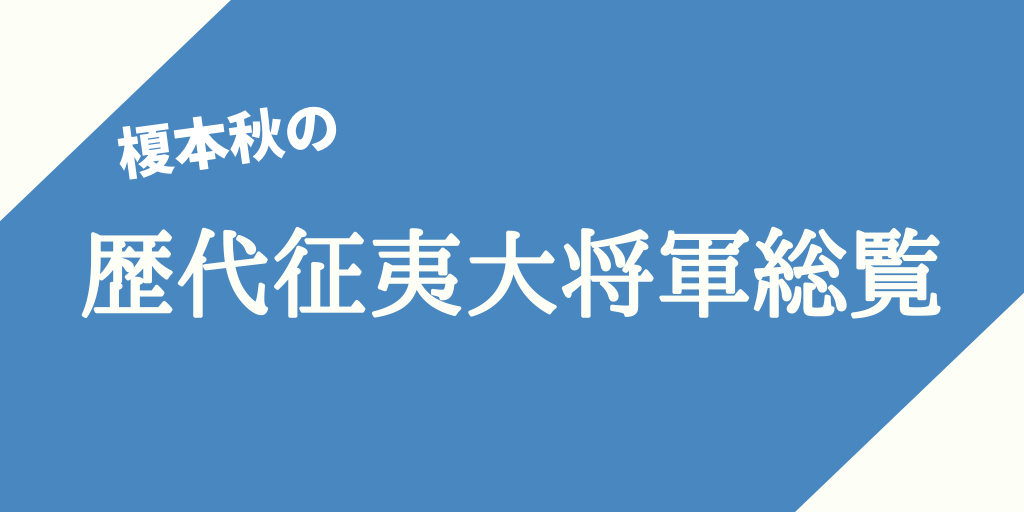
徹底的に翻弄された将軍
4代将軍・藤原頼経(ふじわらのよりつね)の子として生まれた頼嗣(よりつぐ)がわずか6歳で将軍になったのは、1244年(寛元2年)のことである。
先に述べたとおり、2歳で鎌倉にやってきた父・頼経が長じて傀儡将軍の立場からの脱却を試み、先手を打たれて将軍の座を追われたがための将軍就任であった。
本連載で紹介する将軍の中にはその生涯を他者の傀儡として、実権をほとんどもたず生きたものも少なくない。
その中でも特に、頼嗣という人の生涯は哀れだ。彼はまったく使い捨ての道具のように将軍にされて、都合が悪くなったらより良い道具と交換され、放り出されてしまったのだ。
残念ながら、将軍としての頼嗣には特筆するべきことがほとんどない。
彼が将軍だった時代に起きた事件は、彼自身よりむしろ父で先代将軍の頼経に深くかかわる形で起きているからだ。頼嗣という人には、周囲の争いに巻き込まれた犠牲者の影が色濃い。
将軍の地位を無理やり追われた頼経はすぐには京に戻らず、鎌倉に残って復権のための活動をしていたと考えられる。そんな中、執権・北条経時が病に倒れ、代わって弟の北条時頼(ほうじょうときより)が執権職に就いた。
これを好機と見たのか、以前から頼経派であった名越光時(なごえみつとき)が得宗家打倒に動く。名越家は北条一族の中でも得宗家に最も近い名門であり、頼経を擁して自らが執権になろう、という野望もあったかもしれない。この時期には北条氏内部に無数の分家ができていて、それによる混乱に乗じる部分もあったろう。
この「宮騒動(みやそうどう)」と呼ばれる事件の勝者になったのは得宗家であり、時頼だった。光時は最終的に伊豆へ配流され、それ以外の頼経派も多く処罰された。頼経自身も、この事件を機に京へ追放されてしまう。
幕府による処罰はこれだけでは収まらなかった。頼経の父、つまり頼嗣の祖父である藤原道家(ふじわらのみちいえ)が、関東申次(かんとうもうしつぎ)という幕府と朝廷の連絡役にあたる職を辞めさせられてしまったのである。
九条家はその祖である兼実の時代から幕府と朝廷のホットライン的存在であり、彼らがいたからこそ幕府の朝廷政策は円滑に進んできた。
そんな九条家が粛清されたということは、幕府はもう彼らがいなくなっても朝廷に対して強い発言権を行使できるということであり、彼らの朝廷政策がさらに一歩段階を進んだということであった。幕朝関係のつなぎ役としては新たに西園寺家が置かれ、かつての九条家と同じ役割を担うようになった。
それはまた、後ろ盾を失って鎌倉の地にひとり残された幼い頼嗣の立場が風前の灯というのも哀れなほどだった、ということでもある。
とばっちりで将軍の座を追われる
それでも頼経は権力の奪還をあきらめなかったようだ。以後の数年で起きる事件のいくつかに、彼および頼嗣がかかわっていたのでは、少なくとも彼を擁立するつもりで動いていたのでは、という節がある。
たとえば、1247年(宝治元年)に北条氏の挑発を受けて挙兵した有力御家人・三浦氏は以前からの頼経シンパで、頼経を鎌倉に戻すべく動いていたものの、合戦で敗れて自害へ追い込まれてしまった。これを宝治合戦という。
さらに、1251年(建長3年)に僧侶の了行(りょうこう)らが幕府転覆・北条氏討伐の陰謀を企て、露見して処罰された際にも、頼経の名前が出た。この時点で、北条氏としては頼嗣の利用価値に見切りをつけた節がある。
そもそも、概要の項で紹介したように、北条氏は最初から親王将軍をこそ希望していたのであり、摂家将軍はほとんど「つなぎ」程度の意味でしかなかった。かつて後鳥羽上皇の時代に親王将軍を望んだ際にはかなわなかった。しかし、承久の乱での勝利を経て、当時と今では幕府と朝廷の力関係は大きく変わっている。
結果、1252年(建長4年)に後嵯峨天皇の第一皇子である宗尊親王(むねたかしんのう)が鎌倉に迎え入れられると、代わって頼嗣は「父に加担し、北条氏を追放しようとしたのではないか」という疑いをかけられてしまい、将軍職から廃せられ、京へ追放された。それはまさに「用済み」とでも表現するべき処置であった。頼嗣はしばらく京で暮らしたが、父と同じ年に亡くなっている。
このときの頼嗣、わずかに14歳。彼に何か致命的な落ち度などあったはずもなく、完全に「とばっちり」で将軍の座を追われたことになる。
将軍になったときも父のとばっちりと北条氏の都合。将軍を辞めさせられたときも、状況はまったく同じだった。どうにも哀れみを禁じ得ない将軍といえよう。