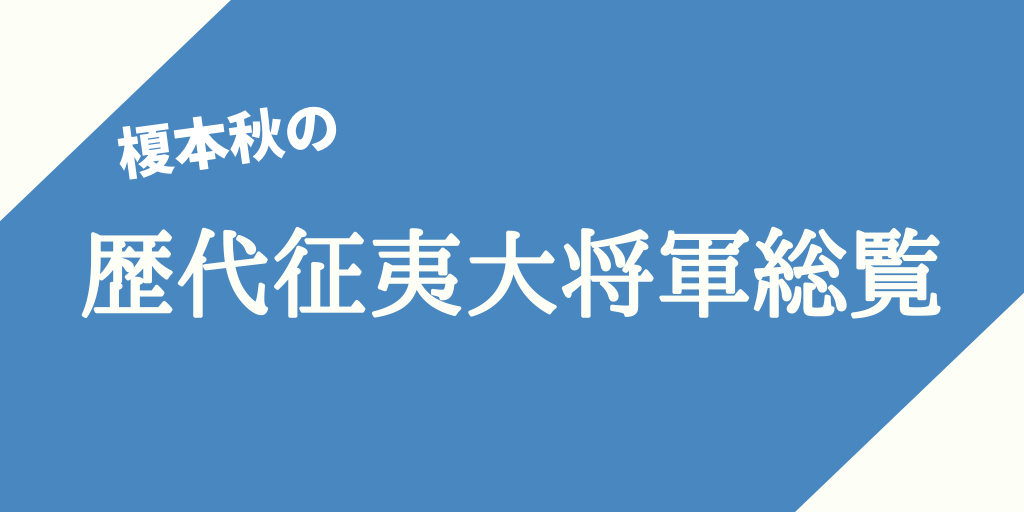
軍事代行者としての将軍
大伴弟麻呂から徳川慶喜まで1000年を超える征夷大将軍の歴史(とはいえ、途中で性質を少なからず変えてはいるのだが)を語るにあたって、まずは征夷大将軍という役職が誕生した古代、奈良時代末期から平安時代にかけてみていきたい。
この時代の将軍と以後の将軍との大きな違い、それは「古代の将軍は幕府の長ではない」ということである。
鎌倉時代以降の将軍は実質的な権限が備わっているか否かという違いはありつつも、武家政権にそのトップとして君臨する存在であった。しかし、古代の将軍は天皇から軍事権を与えられて大きな力を振るう存在ではあったが、あくまで公家政権の一部として機能する存在だったのである。
征夷大将軍とは何のための役職だったのか
古代における征夷大将軍という役職の意味にたどり着くためには、この名前を分解するのが最もわかりやすい。
「征」は征伐や征討の意味であり、「夷」は古代の朝廷にとって大きな問題であった東北の蝦夷のこと。「大将軍」というのは、古代の軍制において3つの軍を指揮する3人の将軍の上に位置する、総指揮官の名である。すなわち、「蝦夷を攻める役目を背負った大軍の指揮官」という理解で問題ないだろう。
ここでポイントになるのが、蝦夷とは何か、ということだ。中世以降、蝦夷は「えぞ」と読まれ、現在私たちが「アイヌ」として知る北海道(蝦夷地)の集団のことを主に指していた。
しかし、古代において蝦夷は「えみし」と読み、これは後にアイヌにつながる文化を持った北海道の集団のことだけでなく、東北地方などに居住して朝廷には従わないが文化としてはかなり近いものを有する異勢力のことも含めて示した言葉であった、という説が現在では有力だ。
蝦夷は狩猟を得意とし、弓と馬を駆使して大いに朝廷の軍勢を苦しめた。
これに対し、朝廷側の勢力拡大は長らく、積極的な武力よりも交渉と移民による部分が大きかった。すなわち、軍事拠点である城柵を設置し、その近辺に柵戸(移民)を居住させることによって、ゆっくりと支配権を拡大させていったわけだ。
有名な出来事として、658年~660年(斉明4年~6年)には阿倍比羅夫(あべのひらふ)による北征が行われているものの、これは蝦夷の各部族と接触して外交交渉を行う、という側面が強かった。軍事力を背景にはしつつも、力ずくで押しつぶす、ということではなかったのだろう。
これらの過程で朝廷に従い、帰順してきた蝦夷は「俘囚(ふしゅう)」と呼ばれ、各地へ移民させられた。
蝦夷との戦い、「征夷」大将軍の誕生
しかし、奈良時代も後期に入ると、状況が変わってくる。俘囚が反乱を起こし、蝦夷の各部族との間に衝突が起きるようになって、朝廷も軍勢を派遣しなければならなくなってきたのだ。
朝廷が積極的な東北進出政策をとったことが蝦夷の反発を招いたこと、蝦夷自体が外部との接触によってそれまでの各部族がばらばらだった状態からある程度の統一ができるようになっていたこと、などが原因であったようである。
これが主に「征東使(せいとうし)」と呼ばれる軍勢で、指揮官も同名、あるいは征東将軍(征東大将軍)と呼ばれた。
その際の役目や戦う相手によってまたさまざまな名があり、その中に「征夷将軍」という呼び名もあったが、制度上正式なのは「征東将軍」のほうだったらしい。793年(延暦12年)にこれが征夷使、征夷大将軍と改められたため、通常「最初の征夷大将軍」といえば794年(延暦13年)に任命された大伴弟麻呂(おおとものおとまろ)のことを指し、それ以前の征東大将軍はそれに含めないことが多い。
ただ、征東大将軍という言葉自体は征夷大将軍の別名のような形で残った。平将門討伐に際して任じられた藤原忠文(ふじわらのただぶみ)は征東大将軍であったが、征夷大将軍のひとりとして理解されているのはこのためであろう。
ちなみにその性質上、征夷大将軍は当時の国家システムである律令に定められた役職ではもちろんなく、「令外官(りょうげのかん)」と呼ばれる制度外の役職のひとつであった。
このように、古代の征夷大将軍の役目は「蝦夷を倒すこと」であった。
そのため、蝦夷の恭順が進んでその脅威が薄れるにつれて姿を消していくのは当然のことだ。イレギュラーとしての藤原忠文以降、征夷大将軍(征東大将軍)は任命されなくなり、再び世に出るのは源平の合戦のころになる。
そのときの将軍は、古代の将軍が持っていた性質をある程度継承しつつも、基本的には別物として歴史に現れることとなるのである。