別名 鶴ヶ城、若松城、黒川城、会津城

会津若松城は蒲生氏郷や上杉景勝など著名な大名が城主をつとめた城です。1643年(寛永20年)に保科正之が入封して以降は明治維新まで会津松平家(保科氏から改名)の居城として用いられ、幕末の戊辰戦争の際には会津戦争の舞台となりました。城址内には会津藩士である西郷頼母、秋月悌次郎らの石碑や銅像があります。現在の天守は1965年(昭和40年)に外観復元されたものですが、さらに2011年(平成23年)に黒瓦を当時と同じ赤瓦に復元しました。また、天守にあるシャチホコは瞳には2カラットのダイヤモンドが埋め込まれています。なお地元では一般的に鶴ヶ城(つるがじょう)と呼ばれています。
目次
会津若松城を攻城した団員が残してくださったクチコミ(レビュー)です。じっさいに訪問した方の生の声なのでぜひ参考に。
会津若松城に関するデータ 情報の追加や修正
230.4 m
内郭:-- 外郭:--
5重5階
25.15 m
11 m
1593年(文禄2年)に蒲生氏郷によって築かれた天守は望楼型5重7階だったとされるが、1611年(慶長16年)に起こった大地震により大破した。その後、その倒壊材を用いて1639年(寛永16年)に加藤明成によって修築された天守は複合式層塔型5重7階(地上5階、地下2階)だったとされる(高さ29m、天守台石垣10.9m)。この天守は明治初年まで存在したが、1874年(明治7年)に取り壊された。現在の天守は1965年(昭和40年)に復元されたものである。当初は黒瓦での復元だったが、2011年(平成23年)3月に赤瓦に復元された。
蘆名直盛
着工 1384年(至徳元年)
1874年(明治7年)
蒲生氏郷、加藤明成
蘆名氏、伊達氏、蒲生氏(92万石)、上杉氏(120万石)、加藤氏(40万石)、松平氏(23万石)、保科氏(23万石)
石垣、土塁、堀
国史跡
天守、門、櫓、長屋
| 項目 | データ |
|---|---|
| 曲輪構成 | 梯郭式 |
| 縄張形態 | 平山城 |
| 標高(比高) | 230.4 m( -- ) |
| 城郭規模 | 内郭:-- 外郭:-- |
| 天守縄張、天守形式 | 層塔型 |
| 天守の階数 | 5重5階 |
| 天守の種類 | 復元(外観復元)天守 天守の分類 |
| 天守の高さ | 25.15 m |
| 天守台石垣の高さ | 11 m |
| 天守の広さ(延床面積) | |
| 天守メモ | 1593年(文禄2年)に蒲生氏郷によって築かれた天守は望楼型5重7階だったとされるが、1611年(慶長16年)に起こった大地震により大破した。その後、その倒壊材を用いて1639年(寛永16年)に加藤明成によって修築された天守は複合式層塔型5重7階(地上5階、地下2階)だったとされる(高さ29m、天守台石垣10.9m)。この天守は明治初年まで存在したが、1874年(明治7年)に取り壊された。現在の天守は1965年(昭和40年)に復元されたものである。当初は黒瓦での復元だったが、2011年(平成23年)3月に赤瓦に復元された。 |
| 築城主 | 蘆名直盛 |
| 築城開始・完了年 | 着工 1384年(至徳元年) |
| 廃城年 | 1874年(明治7年) |
| 主な改修者 | 蒲生氏郷、加藤明成 |
| 主な城主 | 蘆名氏、伊達氏、蒲生氏(92万石)、上杉氏(120万石)、加藤氏(40万石)、松平氏(23万石)、保科氏(23万石) |
| 遺構 | 石垣、土塁、堀 |
| 指定文化財 | 国史跡 |
| 復元状況 | 天守、門、櫓、長屋 |
登録日:2013/11/17 17:35:45
更新日:2024/07/27 03:24:42
会津若松城の見学情報・施設案内 情報の追加や修正
リンク先でチケットを購入いただくと、アフィリエイト広告料が攻城団に入るかもしれません
年中無休
| 項目 | データ |
|---|---|
| 営業時間 |
|
| 料金(入城料・見学料) |
リンク先でチケットを購入いただくと、アフィリエイト広告料が攻城団に入るかもしれません |
| 休み(休城日・休館日) | 年中無休 |
| トイレ | |
| コインロッカー | |
| 写真撮影 | |
| バリアフリー |
会津若松城の見所は城メモをご覧ください



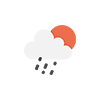
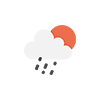
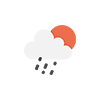
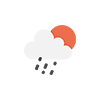

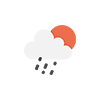
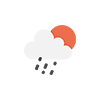
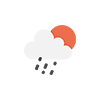
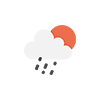
さらに先の週間天気予報については気象庁のサイト 等で確認してください。
会津若松城へのアクセス情報 情報の追加や修正
| 項目 | データ |
|---|---|
| アクセス(電車) |
|
| アクセス(クルマ) |
|
| 駐車場 |
|
じっさいに訪問した方の正確な情報をお待ちしています。
あなたが泊まったホテルのレビューをお願いします!(レビューはホテルの詳細ページから投稿できます)
訪問レポートなど、これまで攻城団に公開された関連記事の一覧です。
まだトピックがありません(情報募集中)
会津若松城をベストキャッスルに選んだ団員によるオススメコメントです。たくさんある場合はランダムに表示しています。
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する