つば九郎さんは72件のレビューを投稿しています。
検索ページ
先だって、この本の姉妹本、日本の城99の謎が、とても読みやすく面白かったので、こちらも手に入れ読んでみました。戦国の合戦の99の謎というよりも99の設問に答えていく形式の、合戦の雑学集、トレビア集といった内容です。すべての設問が見開き1ページで簡潔にまとめられていて、左ページは関連する写真や図が掲載されています。白黒で小さいのが、やや見ずらく残念ですが、小田原城や上田城といった合戦の舞台となった城の写真もたくさん載っています。また、合戦の屏風や武将の肖像画等々の資料としても、なかなか見ていて面白いものが多い気がします。小さいのが、ただただ残念ですが。
自分にとっては、城の謎の本の方が知っていたよという話が多く、こちらの合戦の謎の方が知らないことが多い分、より楽しく読めた感じでおりますが、はなから歴史に詳しい方や合戦好きの方からすると、もの足りないよということもあるかもしれません。自分は、あっという間に読めて、川中島、関ヶ原から戦場のトイレ事情まで、十二分に楽しめる事ができました。

漫画センゴク権兵衛編の第20巻まで読み進めてまいりました。ここがこの一大戦国大河ドラマのついにクライマックスでしょうか。主人公、仙石秀久は、九州征伐での大失敗から改易され、一旦故郷である美濃に戻り、そこから高野山に向かい修行を通して人間らしさを取り戻し、なぜか顔付きさえも良くなった気がしております。最大級にやらかしちゃったけど、しっかり反省して、人間的に成長して、さあ次へです。ここがあったからこその小田原合戦での大復活ですね。
さてその小田原合戦は、今現在、神奈川県に住み小田原城を自分の本城とし、おそらくかなりの回数、ここに足繁く通っている身とすると、そりゃもう面白い限りですね。さらに大好きな山中城、石垣山城も、そこには当然登場してくる訳で、思い入れがある分気分も上がります。そして、小田原城の総構えの防御の凄さたるや、最強の城の称号に恥じない強さを発揮します。今日今からでも、訪ねられる城が舞台になっていることの幸せすら感じます。(実は愛知、滋賀に住みたい。内緒)
たいへん面白く、楽しい毎日を過ごさせて頂いたセンゴクシリーズも、もう残りわずかとなってしまいました。最終章は、桃山波濤編になるようです。歴史物の長編小説も残りのページが少なくなると寂しくなってくるのと今は同じ感じでしょうか。きっとこの漫画が司馬遼太郎並みに面白かったからでしょうね。

長谷川ヨシテルさんの「ヘンテコ城めぐり」が面白かったので、こちらの最初に書かれた著作も読んでみました。ポンコツな逸話を数多く残してしまった、戦国武将達への愛にあふれまくった人物名鑑です。こちらの本も、もちろん面白かったです。
登場している武将達のパターンとすると、一つは、親が信長やら家康やらで、あまりにも偉大すぎて、そりゃ比べたら可哀想だろうパターンと自分の趣味に走り過ぎたり、酒に溺れ過ぎたりで力の入れどころが違うだろうパターンがあるようです。
自分なんぞは、こんなにも平和な時代に極めて普通の家に生まれ育ち、何のプレッシャーもなく、ここまで生きてこられたことは、ありがたい限りだと思います。ましてや、自分の息子と娘には、プレッシャーのかけらすらない、この平凡を絵に描いたような親の元で育ったことを途轍もない幸せと切に感じて欲しいものです。おいおい、そこはそうじゃないだろうと。
この本の最後の方には、臆病・狡猾編があって、攻城団で勧められて、今まさに読み進めている漫画センゴクの主人公仙石秀久も登場しております。失敗もあったけれども、ずっと諦めない姿勢が彼にはあったと暖かいフォローがなされております。ポンコツな武将集の本なのに、実は自分の生き方を見直せる素敵な本なのかもしれません。

漫画センゴクシリーズもいよいよ最終盤で権兵衛編の第10巻まで読みました。主人公、仙石秀久も讃岐一国の大名へと大出世してまいりました。最初、一兵卒に過ぎなかったのが、当人の頑張りと、部下の活躍、そして秀吉に仕えたことがやはり大きく、負け戦なくここまで邁進してきております。ある意味、裏を返せば秀吉の出世物語でもありますね。
全国統一も、あともう一息、まずは四国征伐で長宗我部氏と戦い、和議に持ち込みます。長宗我部氏の人たちは、できた方々で九州平定では秀久と一緒に戦うことになります。ここまで、すべてが怖いぐらいにうまく行き、躍進し続けてきた秀久でしたが、そうそう良いことばかりが続く訳ではないのが人の世の常ですよね。そうじゃないと人生、面白くないですしね。この漫画、実は負けていく側の武将達への愛があふれている漫画なような気が、ずっとしております。
センゴクシリーズ当初から予告され続けていた、秀久の大失敗が、ここで発動されました。ここまで勝ち続けてきた慢心と焦りでしょうか、これまで周りの意見にはきちんと答えていたんですが島津氏相手に大惨敗を喫してしまいました。逃げる途上の失意の中10巻は終了です。この後の大復活も、当初から予告されておりますので、愛ある復活を期待しながら、この先を楽しみにしたいと思っております。

漫画センゴク第3部となる一統記も、最終巻15巻まで読み終わりました。秀吉による天下統一への道は、光秀との山崎の戦いから勝家との賤ヶ岳の戦いを経て、信雄、家康との小牧・長久手の戦いまで進んで来ました。信長の跡目争いの戦いで昨日の友、仲間は今日の敵といった戦いが続き、戦略が複雑化し、双方の腹の読み合いが相当に面白いです。
自分は、この夏、名古屋まで攻城しに行っており、その時に小牧・長久手の戦いの舞台となる犬山城、小牧山城を攻城しておりましたので、今回の興味、楽しみが格段に増したような気がします。実際に訪ね、自分の足で立って、見て感じることが、やっぱり一番良いことなんでしょうね。実感。
さて、主人公の仙石秀久は、この間、四国で長宗我部氏と戦いを続けており淡路の大名へと出世してきておりますが、自分はそれほど歴史に詳しい訳でもないので、だからこの漫画も楽しめているのかもしれませんが、秀久がすると予告され続けている失敗のことを何一つ分かっておりませんので、何を仕出かすのか、この先の最終編の権兵衛編を楽しみにしたいと思っております。

宮下英樹さんのセンゴク一統記も10巻へと読み進んでまいりました。本能寺の変が終わり、山崎の戦いが始まりました。
今は、プロ野球の大一番を決する試合の際によく使われることが多い天王山の戦いこと山崎の戦いですが、自分は実はそれほど詳しく内容までは分かっておりませんでした。ドラマ等を見ていても、どうしても本能寺の変がメインに描かれることが多く、山崎の戦いはあっさりと言いますか、毎週楽しみに見ていた「麒麟がくる」に至っては、まったく触れられもしませんでした。はじめて、ここまで細かく詳細を、この漫画で知ることが出来ました。
自分は、光秀は細川、筒井の支援を受けられず、割とすんなりと秀吉が勝ったんだとばかり思っていたんですが、天王山の戦いが雌雄を決する試合に使われるように、かなり際どい凄い戦いだったことが分かりました。戦国時代の合戦は、掘り下げれば掘り下げるほど、奥深く面白いです。
まだまだ合戦続きの状況ですが、ここに来て、かの運命の三姉妹が登場して来て、絵面が急に華やかになりました。最初の頃は、けっこう艶っぽいシーンも多かったんですがね、まぁとは言え、次は賤ヶ岳の戦いですので、ここも掘り下げて頂けることを期待しております。

センゴク第3部一統記編を読みはじめ、5巻まで読了しました。ついに本能寺の変ですね。間違いなく日本の歴史史上最大の出来事の一つですね。
さまざまな、憶測も語られてしまいがちな事件ですが、この漫画では、割とオーソドックスな描かれ方だったかなと思います。そこは、自分はかなりの好感触です。
この漫画では、黒幕の存在等は、いっさい無く、光秀単独説に立っており、理由は信長自身が日頃から下剋上を奨励するようなことを語っており、光秀の野望による謀叛の立場を取っています。良く言われる怨恨説の立場は取っておりません。あまり、自分なんぞが書きすぎると、これから読もうとしていらっしゃる方に申し訳ないので、この辺でやめておきます。実は自分は、かつて子供の頃に見た大河ドラマ「国盗り物語」の印象が非常に強くて、濃姫(帰蝶)も信長といっしょに槍で戦い、最期は、人生50年の謡を舞うもんだと思い込んでいた頃がありました。自分の歴史観は、ほぼ司馬遼太郎さんに影響されてしまっているんですよね。
さて、光秀の心情も分からんでもないとする秀吉の中国大返しまで話は進み、次は山崎の戦いや賤ヶ岳の戦いですかね。夜寝る間を、惜しんで読み進める日々が続いていきます。実に楽しいです。

センゴク第2部天正記、最終巻となる第15巻まで読了しました。
歴史的事実な訳ですので、当然そこは、如何ともしがたいところですが、ここでの竹中半兵衛の死は、やはりグッとくるものがありました。最期の方の、軍師としての冴え渡り加減は、凄すぎでした。また、半兵衛の病の湯治のために有馬温泉への道を確保しようと城攻めを命ずる秀吉も、なかなか素敵です。
またこちらも、歴史的事実ではありますが、信長包囲網の最大の黒幕として、余りに不気味な姿でずっと描かれ続けてきた、本願寺総帥・顕如が、まあ割とあっさりと信長との和睦を受け入れたのは、知っていたとはいえ、まぁそうなるよなという感じでしょうか。
この第2部天正記は、武田勝頼が死すところまでが描かれましたが、合戦中心ばかりではなく、楽市楽座や検地、貿易港の確保といった経済的な話も増えてきた感じがします。武将というのは、確かに武力を備えて戦に勝ち続けていかなければならないのですが、一方で、領地領民を抱えて経済も回して行かなきゃならないので要は政治力に優れていないといけないんだよなという気がいたします。その代表格と言える、石田三成も、いよいよ登場してまいりました。
話しは、第3部一統記編へと進み、本能寺の変が始まるようです。光秀はいったい何故は、どう描かれるのか気になり、楽しみなところです。

センゴク天正記の10巻まで、読み進めてきました。織田信長の侵攻範囲が、グッと広がり、いよいよその地位を確立していく反面、広がりすぎによる齟齬やら、信頼筋からの謀叛も起きはじめてきています。攻城団的には、安土城が姿を現し、今後の展開への伏線でしょうか、信長が建設途中の城を背景に部下、民衆に下剋上推奨の演説をぶち上げます。
北の侵攻は、ついに上杉謙信との直接対決へ、南の侵攻は雑賀集との戦いへと進み、刀、槍、馬がメインから銃と調略そして補給路断絶へと戦い方が変わってきました。特にそれが顕著となるのが西方の背後に毛利が控える侵攻で、秀吉、半兵衛の本領発揮ですね。そして、大砲備えた船の戦い方へと新しいやり方に対応していける信長の資金力の凄さですね。
そしてそこには当然、荒木村重の謀叛もあり、自分の大好きな武将、黒田官兵衛もいよいよ登場してまいりました。この漫画は、そこが面白いところでもあるんですが、登場する武将の絵面がエキセントリックすぎになる傾向があるので官兵衛どうなるかと思って少し心配していましたが、割と普通の姿で出てきたので安心しました。官兵衛、この先いっぱい登場してくれると自分は嬉しいですが、それも楽しみに読み進めていきます。

漫画センゴク第2部となる、天正記1巻から5巻まで読み進めました。我らが主人公、仙石権兵衛秀久も出世し、文字通り千石の拝領地を持つ武将となり、家臣を持つ身となりました。5巻ともなると、嫁を娶る話へと進んで参りました。お嫁さん、この先、面白くなりそうな人で楽しみです。
歴史的合戦の話は、ほぼほぼ織田、徳川軍対武田軍の長篠の戦いに費やされています。これもすごい戦いですね。ここまで、当然、もう1人の主役は織田信長な訳ですが、今回その恐ろしさ、非情さ全開ですね。鉄砲を使った、殲滅戦へと戦い方が大きく変わっていったことが、良く分かります。
敗者となる、武田側ですが信玄亡き後、勝頼を盛り立てて、結果、戦に散っていく武将たちが見応えがあり、素敵すぎです。さながら西部劇にありそうな展開で倒れていく真田源太左衛門信綱が今回では一番のお気に入りでしょうか。今後真田家は、あの面々が仙石家との戦いの曲面で深く関わっていくことが予告されたので、そこは期待大です。
さて、人間的にも仙石権兵衛秀久が、かなり成長してきたので、今後の先の巻を、さらに楽しもうと思います。

皆さんからのお勧めのセンゴクという漫画に、すっかりどハマりし、ついに15巻まで読み進みました。一乗谷の戦いから小谷城の戦いに、話しは進んできました。小谷城の戦い、これがもう、凄いことになっております。
小谷城の大手口、畝堀、曲輪群の3つの難関を撃ち破り、さらにその先に控える虎口を、どう攻略して行くのか、まさに山城攻略の難しさと凄さを思い知らされます。そして一方の山城の防衛力の、素晴らしさも実感させられます。これまで、自分も、幾つかの山城に実際訪れていて、この目で竪堀も見てきていたんですが、よく分かっていなかったようです、これからは見る目が変わってきそうです。
小谷城は当然いつか攻城しに、伺わない訳にはいかなくなってしまいましたね。これから攻城する方は、このセンゴクの13巻から15巻は必ず目を通してからの方が絶対楽しめると思います。すでに行った方も再訪したくなると思います。
秋の夜長に、じっくり読み進めていきたいと思いますなどとのたまっておりましたが、あっという間にセンゴク第一部を読み切ってしまいました。主人公、仙石権兵衛秀久の人生からすると、ここまでは、まだまだ序の口でしょうから、この先も楽しめそうです。早いところ、天正記編をレンタルしに行かなくちゃ。

攻城団の読者投稿欄で、皆さんからお勧めされた、宮下英樹さんのセンゴク、10巻まで読み進めました。イヤー、ますます盛り上がり、面白くなってまいりました。
主人公、仙石権兵衛秀久は19歳から21歳まで、比叡山延暦寺焼き討ちから三方原の合戦までが描かれています。信長包囲網が石山本願寺を中心に進んでいく訳ですが、包囲網側の思惑や戦略も丁寧に描かれているので、歴史観も、とても分かりやすくなっています。漫画だからと、侮ることなかれ、かえって理解が進むます。漫画恐るべし。
8巻の終盤になって、武田信玄公が、のそっと登場して参ります。その姿、描き方が、映画「地獄の黙示録」のマーロン・ブランドのカーツ大佐に、瓜二つで自分的には、かなりのツボです。
10巻は三方原の合戦までで終わりますが、最後のコマは、自分が今年、名古屋遠征した際に徳川美術館で見た「しかみ像」(岡崎城にあるしかみ像の銅像の元絵)になっております。
11巻、早く読まなくては。

つい先立っての読者投稿欄での、お題が戦国時代、江戸時代を舞台にした、お勧めの小説、漫画を教えてくださいでした。その結果、最多となる3名の方が、挙げてくださっていたのが、このセンゴクという漫画でした。自分は、まったく知らない漫画でしたので、これは早速読まない訳にはいかないだろうと、いまや貸漫画業が、すっかりメインになりつつある近所のTSUTAYAに赴き、レンタルしてきました。まぁ便利な世の中になったものです。
今回は、まず最初の1巻から5巻までを読んでの感想です。実在した仙石権兵衛秀久を主人公に、彼の15歳から18歳まで、稲葉山城の戦いから姉川の戦いまでが描かれています。ここまでで、すでに三英傑をはじめ、錚々たる戦国武将が登場し、8割方が、合戦のシーンで劇画タッチの絵面が迫力満点で、面白いです。
これは、皆さんが勧めてくださるはずです。まだ序盤ですが、すっかりハマってしまいそうです。読書の秋の夜長、ゆっくりと読み進めていこうと思っております。この漫画を、勧めてくださった皆様、改めてお礼を申し上げます。ありがとうございます。

れきしクンこと、長谷川ヨシテルさんのお城紹介本です。youtubeでも知られ、前田慶次さん、萩原さちこさんとの城巡りの回は、毎度楽しく拝見させていただいております。ちなみに自分は登録者のひとりです。
そんなにヘンテコでもない気もしますが、独特の切り口が、非常にクセになる面白さがあります。何より表紙からして、もう面白いです。自分は、基本100名城と続100名城を中心に城巡りをしていますが、日本中にある、それぞれのお城には、それぞれの歴史があり、それぞれのエピソードがあるんだということを思い知らされます。
五稜郭の仲間たち、いっぱいある二条城、一夜城あれこれ、映画やドラマのロケ地の城等、テーマを考えればまだまだ、無限に城巡りの可能性が広がることも教えてくれます。
そして、あとがきまで読んでくると、いつもお世話になっているインターネットの城サイトに感謝の気持ちを込めてと紹介されている6つのサイトの中に、なんと攻城団が!。見学時間の目安が記されているので、スケジュールを組む時に非常にありがたいと書かれております。

お城好き、とりわけ石垣好きには、堪らない一冊です。お城といえば、この人、小和田哲男さんが書かれた本です。残念ながら、掲載させている写真が、すべて白黒なのと、地の文章がピンク色になっているところが多いので、目が慣れないと読みづらく感じる方がいらっしゃるかもです。自分は、かつて参考書に引きまくった、マーカーの蛍光ピンク色を思い出しました。
第壱章は、知っておきたい石垣の基礎知識となっていますが、基礎じゃないでしょというレベルで書き込まれています。石垣のつくり方も、調達から積み上げまで、凄い労力だろうなと思わされながら、絵図で分かりやすく説明してあります。
第弐章、第参章は、北は北海道から南は沖縄まで、石垣の名城75城が、石垣に特化して詳細に解説、説明されています。巻頭で「豆知識」のところを読むだけでも城石垣のスペシャリストになれますと書いてありますが、どこを読んでも見ても、物凄い情報量です。石垣ですので、そこは当然、西日本のお城の方が、比率は高く紹介されています。ぜひ、同じ形式で名城の土塁図鑑も出していただきたいところです。
自分は、かなりの石垣好きで、石垣は必ず眺めるだけでは飽き足らず、直接実際に手でさわってみるぐらいなので、ありがたい一冊です。

ひじょうに分かりやすく、読みやすい本です。お城の楽しい雑学、エピソード集で誰かに話したくなるトリビア集といった感じの一冊でしょうか。一応99の謎が、まず提示される形になっていますが、まあ取り上げたい内容が先にありきではないでしょうか。
本当に読みやすく、自分は我がスワローズの試合を観戦しに神宮球場へ行く往復の電車の中で3時間程で読了しました。(ちなみに最近、画像を変更しましたが、この時の試合の村神さまのヒーローインタビューの写真にしてみました。他球団ファンの方はすいません。)はなから知っているよと言う話も多かった反面、へぇそおなんだという話もいっぱいありました。
土方歳三は城攻めが上手かった?、童謡とうりゃんせは川越城で生まれた?、忍者はどうやって城に侵入した?といったエピソードが、自分には面白かったです。
なかなか、面白い本だったので、シリーズで戦国の合戦99の謎という本も出ているようなので、その内読んでみようと思っております。

お城のムック本ですが、戦国武将と絡めて紹介していくスタイルになっています。したがって、登場してくるお城は、どうしても戦国時代以降のものが中心となっております。13人の戦国武将は、上杉謙信、伊達政宗、前田利家、武田信玄、毛利元就、太田道灌、北条氏康、織田信長、豊臣秀吉、長宗我部元親、真田昌幸、藤堂高虎、丹羽長秀のビッグネームが並び、ゆかりの城が紹介されています。
フランス人の女性の方が、彦根城や、その城下町を旅するレポート等、独自の記事が掲載されていて、他には見られない面白い内容になっています。
最近、映画化されている、時代劇が経済的観点から描かれている作品が多い気がしていて(決算忠臣蔵、超高速参勤交代)、ぜひ大河ドラマや映画で、加藤清正あたりの城造りや町造りをメインにして作っていただけないかなと思っております。
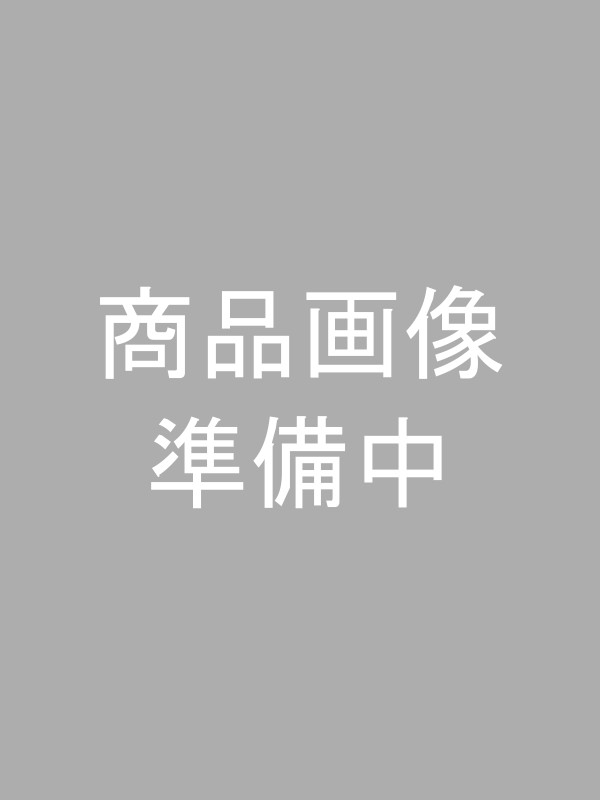
お城関連の本は、当然、世に数多くあり、各地の名城を紹介してくれている本、天守やら(なかには、あやしい天守閣やら)石垣やらに特化している本、大名からや合戦から、歴史サイドからアプローチしたお城の本、1城だけに限定した本、専門的な本から雑学的な本、そして子供達に向けられている本、等々、さまざまなバラエティーさで出版されています。そのすべての本で、ありがたいことに、お城の基本用語や石垣の積み方、天守の構造、城の歴史といった、お城初心者が最初に知っておくべき項目にかなりのページが使われております。
これは非常にありがたいことなんですけれども、ただ今回は、お城のあの事について調べたいんだけど、どの本のどこに書いてあるのが1番分かりやすかったけなーということが、自分にはしばしばあります。自分だけかもしれませんが。
そんな自分のようなタイプの者には、そしてそこのあなたには、この号の歴史人です。なにしろ、日本の城、基本のきです。城の見方を徹底解説し、知っていれば城歩きが100倍面白くなる本です。
各項目、それぞれの専門的に書かれた本を除けば、ほぼこの本が1番詳しく、かつ分かりやすく説明してくれていると思います。そして、この本、一冊あれば良いんです。さながら雑誌でありながらの、間違いなくお城の百科事典と言える一冊です。
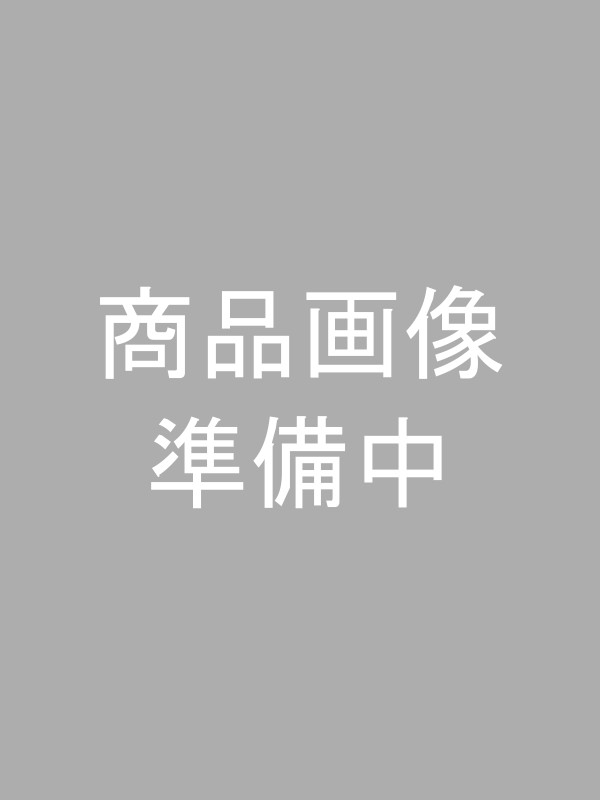
先日、攻城団の読者投稿欄でも、取り上げられた最強の城だけをテーマにした雑誌です。というか、城好きは誰もが一度は自分なりの思いを巡らせるテーマかもしれません。攻城団では、江戸城、姫路城、熊本城の3城を挙げる方が多かったですかね。ちなみに自分は大坂城でした。
さて、結局どの城が最も堅城なのか、雑誌歴史人の見解は如何に。
加藤理文氏、中井均氏、三浦正幸氏の三氏が、
縄張、曲輪、土塁、石垣、堀、地形、規模、虎口・門、櫓、天守の10項目で採点して、合算して総合ランキングを選出しています。
総合部門ランキングは1位から順に姫路城、名古屋城、大坂城、江戸城、広島城、彦根城、熊本城、伊予松山城、岡山城、会津若松城でベスト10となりました。大坂城と江戸城は同点3位です。結果、近世の天守を備えた大型城郭が並んだ感じでしょうか。
11位以下の方が、津山城、和歌山城、小倉城、駿府城、萩城と並び興味深いですし、部門別ランキングの土塁で諏訪原城が堀で佐賀城が1位に選ばれており、細かく見ていくと、なかなか面白いです。
城好きは、それぞれに自分なりの思い入れもあるでしょうし、ランキングは122位まで挙げられているので飽きることなく読んでいられる1冊です。

昨年、出版されたばかりの本です。この手の全国のお城の紹介本とするとおそらく最新刊となると思います。東日本編、西日本編、の2冊で50城づつ計100城です。東日本編で滝山城と八王子城、長篠城と古宮城が、それぞれ1城の扱いになっているので、正確には計102城です。
そこは最新の本ですので、各城の情報の内容への信頼性は高く、御城印情報も充実しています。オールカラーで掲載されている写真も、非常に綺麗で、サイズ的にもコンパクトなので持ち運びにも便利です。
名城を訪ねる旅となっており、各城ごとに、おすすめ立ち寄りスポットが掲載され、城によっては、旅情を味わうモデルコースが、美味しそうなメニューを伴って登場しております。千田嘉浩さんのひとこと解説も当然、的を得ていて楽しいですし、巻末の名城みやげも、こんなものもあるのかと思わず買いたくなってしまいそうです。二条城のカプセルトイのフィギュアコレクションが気になりすぎです。同じものばかり出し続ける羽目になって散財しそうですが。
最新の情報が得られる充実の内容で、間違いなくお勧めの2冊です。1冊じゃないんかい。

タイトルは日本三百名城となっており、確かに新たな100城が選出されていますが、内容的には、ほぼその100城とは関係無く、ごくごく至って普通のムック本です。せっかく、更なる100城を選んだんだったら、その選出理由や紹介に徹すれば、かなり面白い内容になっただろうになぁと思えて残念です。
地域的なバランスの悪さが、気になるところではありますが、四稜郭、宇都宮城、久留里城、河村城、墨俣城、久能山城、清洲城、玖島城、杵築城、等々が、更なる100城には選ばれております。このあたりまでは無難だし納得の選出でしょうか。
まぁ、お城マニアは、当然すでに自分なりの300名城選びを空想していたりすると思うので、答え合わせ的な楽しみ方はできる一冊かもしれません。

お城好きの端くれとして、お城の魅力は天守だけではないということは、十二分に分かってはいるんですが、とはいえ、やはり模擬天守でも見れば気分はグーンと上がるし、当たり前のように写真に収めてしまったりもする訳であります。
数々のあやしい天守閣たちも、あやしいながらも地元の方々の熱い思いがあり、観光資源としての大きな期待があり、地方行政の在り方までも考える良い機会を与えてくれます。巻末に書かれている、城郭・戦国史研究家の方の、お城ファンはなぜ「ヴィヨンの天守」の夢を見るのかにある、あやしかろうと、いかがわしかろうと、存在し始めてしまったものには、何かしらの意義が宿ると言う文章が重いです。
そして、反面教師ではないですが、だからこそ12城しか残っていない現存天守は大切に保存していかなければならないという思いを強くします。また、現存櫓、現存門、4つしかない現存御殿も大切にしていかなきゃならないですね。そして、今後の復興も、きちんとした復元として後世にあやしいと言われないものにしていかなきゃならないですね。
下田城じゃない、下田城美術館(廃館)のぼろぼろになってしまった悲しい姿が、あちらこちらに広がっていかないことを心より願っております。

関東圏では、コンビニでも販売されている、街巡りの雑誌「散歩の達人」から出ているムック本です。2017年発行とやや情報が古めなのと、雑誌の傾向からほぼ首都圏から行けるお城ばかりなのが残念ですが、これはかなりお勧めの1冊です。
お城や古戦場の紹介だけではなく、その近辺にある神社や関連施設も詳しく説明されており、詳細な地図で、お散歩コースとして案内されています。各所間の徒歩でかかる、おおよその時間の目安まで書かれている親切さです。トータルの歩行時間と歩行距離付きです。もちろん、そこは散歩の本なので食事ができる店も詳しく紹介されています。
自分は、城だけではなく、旅として城巡りを楽しみたいタイプですので、この本はありがたいかぎりです。また自分は関東住みなので、すでに攻城済みのところが多いのですが、こう回れば良かったのかと後悔しており、逆に再訪を企んでおります。
やや古い本ですので、入手が難しいかもですが、図書館や古書店で見かけたらぜひ。ちなみに自分は大手古書チェーンのネット販売からの200円での購入です。

4つのテーマから城のプロが選び抜いた、本当に行くべき100城が紹介されているムック本です。ただ、最後まで読んでも城のプロとは誰なのかは残念ながら分かりません。4つのテーマは、「現存天守と定番の城」25城、「有名大名ゆかりの城」30城、「今、話題・注目の城」20城、「風光明媚な城」25城となっていて、合計で100城です。
各城の御城印の紹介には、力が入っていて、大きめの図版で、価格、購入できる場所、発売年月が記載されております。100城以外の城も、厳選全国のオススメ御城印セレクションというコーナーで紹介されております。
オールカラーのムック本ですので、当然綺麗な写真も多く、眺めていて飽きない、攻城初心者向けの一冊になっております。

完全ガイドシリーズというムック本の中の1冊のようです。ナンバーは244となっていますので、他にも色々シリーズの本があるかもです。
巻頭特集が天守を極める!となっているように現存をはじめ復興・復元天守があるお城がメインの紹介、解説本になっています。山城は絶景山城ランキングと歩き方というコーナーに10城まとめられておりますが、山城ファンには少し物足りない内容かもしれません。
各城の古地図の縄張り図が掲載されているのと、天守の断面図のイラストが描かれているのが分かりやすく、なかなか面白いです。そして、ムック本ですので、お城の写真はどれも綺麗なものが多く、自分が写す際の良い参考になります。
なぜか、最後のコーナーが、地理と地形で読み解く戦国の城となり、兵糧攻め、水攻め、力攻め、奇襲戦、調略・情報戦のそれぞれ代表的な城攻めが紹介されていて、陣容図、方位図も示されていて、読み応えがあります。兵糧攻めは鳥取城の飢え殺しが、水攻めは備中高松城攻めが紹介されたおります。

とにかく、お城の写真を日々眺めているだけで、時間が潰せているぐらいだし、自分が攻城する際の、写す参考にしたいなと思う気満々なので、お城関連のムック本をたくさん集めています。その延長で、更にきれいなお城の写真をと購入したのが、こちらの1冊となります。
写真図鑑と銘打っているだけあって、さすがに美しい写真が多いですし、登場する城数も103城と、結構な数ですし、各城5〜10枚づつと、なかなかの見応えになっております。とはいえ、ページ数は95ページとひじょうにコンパクトに、まとめられております。2017年発行ですので、掲載情報はやや古めではありますが自分にとってはお城のミニ写真集です。
自分の息子が、美術展に行くたびに、名画や気に入った絵の絵ハガキを買ってきて、それを100均の額に入れて部屋の壁に貼り付けて飾るという、結構面白いことをやっていて、ちょっと羨ましく思っていて、自分はこれを自分で撮ったお城の写真でやりたいなと今は考えています。この小さな夢を実現するために、今日もお城の写真を眺めて、攻城計画を練っております。

笑点の司会として今やお馴染み、そして、大好きで毎回欠かさず見ているNHKテレビで不定期に放送されている、最強の城スペシャルの出演者でもある落語家、春風亭昇太師匠による1冊です。番組等でも公言されているとおりに、中世城郭の山城愛が爆発しております。
そして、そこはさすがに師匠、全編にわたって笑いを散りばめながら、ひじょうに読みやすい語り口で、お城愛が綴られています。一方、想い出の庵原山城に立つもの、といった人情噺も語ってくれております。
巻末には、同じく城あるき好きの歌舞伎俳優、坂東三津五郎さんとの楽しい対談も、掲載されています。
また、巻頭には、城あるき適性チェックシートなる50問の面白い設問が用意されていて、自分も早速やってみたところ、33のチェックが入り、31〜40は、「もう何も言うことはありません。あなたは身も心もお城好きなはず。全国各地のお城あるきを今すぐスタートしてみましょう。っていうか、もう行っているでしょ。」ということで、すっかり当たってしまっておりました。皆さんも、ぜひチェックしてみてください。
全編にわたって、昇太師匠の、お人柄とお城愛に浸れる1冊です。

攻城団で出している本ということもあり、すでに20件ほどのレビューも挙がっておりますが、この本が出てから、わずか2年で状況が、さらにもの凄い勢いで変わってきており、そこも踏まえて書かせていただきます。まず、この本に関しては、御城印に特化した素晴らしい作りになっており、攻城団でお馴染みのマーク、写真にはよく知る方々のお名前が、それだけで嬉しくなってしまいます。
御城印の元祖は、調べてみると30年ほど前、平成の始まった頃に松本城で作られたものが最初のようです。平成25年の伊勢神宮の式年遷宮から寺社巡りのブームが始まり、パワースポットを目指す人が増え、かわいい御主印を集めるという一代ムーブメントになっていき、それを追いかけるように御城印を出すお城が増え、お城好きたちを後押しすることになりました。2年ぐらい前は、城跡が神社になっているようなところでは、自分だけが御城印で御主印を書いていただくのに列になって並んでいる方をよく見かけておりました。ただ、コロナとなり、外出制限と御主印も書き置きになってしまい御主印ブームは一旦収束してきているようです。
もともと書き置きだった御城印は、この本が出た時が、316城で、皆さんが書いてらっしゃるようにすでにボリューム満点でしたが、今現在攻城団では1195城と2年で4倍となり、新たに武将印や合戦印なるものも登場してきております。城好きの端くれとしては、ありがたいことでもあり、嬉しく喜ばしいことですけれども、ここまで増えてくると、もはや個人ですべてを集められる範囲をとうに超えており、自分なりの条件をつけて(百名城に絞る、地域を絞る)付き合っていくことになるのかなぁと思っております。また、あまりにブームになって高額でやり取りされたり、一気に忘れさられてなくなってしまうことなく末永く御城印が続いていっていただけることを願っております。売れなくなれば、経済原則で淘汰されますからね。
次に本を出す時は、厚さ4倍ですかね。値段は2倍ぐらいまででお願いします。あるいは、もうネットの時代ですかね。

日本にある、いわゆる天守閣を140城、完全名鑑として紹介してくれているムック本です。色々言いたいこと、考えさせられることだらけですが、この本を読んでいくと何故か逆に140城もあるんかいとも思ってしまいます。反面教師的になってしまいますが、だからこそ12城しかない現存天守は、これから先ずっと大切に保存していかなければならないと思わされますし、城ブームの折、この先、再建される施設はきちんとした復元、復興を目指していただきたいものだと思います。きちんとしたものを作った方が、結果的に集客に繋がると思うんですけどね。そして、城マニアの端くれとして思うのは、城の魅力は建造物や、ましてや天守だけではないんだぞというところでしょうか。
この本の最大の読みどころは、あやしい天守としてまとめられているコーナーでしょうか。自分は、仕事の関係で長く茨城県に住んでいたことがあり、あやしい天守の筆頭とも言える豊田城じゃない、常総市地域交流センターの前を車でよく運転しておりました。じゃないのに、その立派なことと言ったら、どうせ作るなら目立ってなんぼ、話題になってなんぼなんでしょうが、調べてみたら30年前ですが建設費用は18億で、総費用は21億だそうです。いわゆるバブルの象徴ですが、作ったからには活用され続けていただけることを願っております。あの2015年の鬼怒川が氾濫した災害時には、避難所として利用され活躍したことは付記しておきます。
そして、出版社は違うようですが、他であやしい天守閣としてまとめられた本も出ており、こちらもひじょうに面白い一冊となっております。こちらもぜひ。

お城を実地で楽しむために、7つの項目を挙げ、「石垣」「天守」「櫓・門・御殿」「山城」「縄張」「合戦の舞台」「戦国武将」、それぞれの項目にあった魅力的な城を日本100名城から4城づつ、計28城で判りやすく優しい語り口で説明してくれている1冊です。オールカラーで掲載されている写真は小さく細かいものが多いですが、魅力を上手に伝えてくれており、自分の撮影の参考になります。登場するすべての城に城内MAPが掲載させており、これがひじょうに判りやすい地図になっております。
ただ一方、各項目以外の説明は極端に少なくなっていたり(ほとんど無かったり)、28城以外の城の紹介はワンポイント見どころガイドに、まとめられてしまっていたりと100名城をとにかく知りたいんだ、この部分のこの箇所が知りたいんだという人向けではなく、通して読むことでお城の魅力が伝わってくる1冊になっております。
なお、この本から1年半後に続100名城バージョンも出版されており、「石垣」「縄張」以外は「立地」「城の変遷」「歴史的舞台」「絶景」「城下町」とよりディープな項目になりページ数は143ページから実に205ページへと、かなり増え(価格は300円up)語り口も変わらず優しいながらもより熱くなり、城マニアあるあるの100名城は正より続が実は魅力的を実感できる内容になっております。
書籍を検索してレビューしましょう。
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する