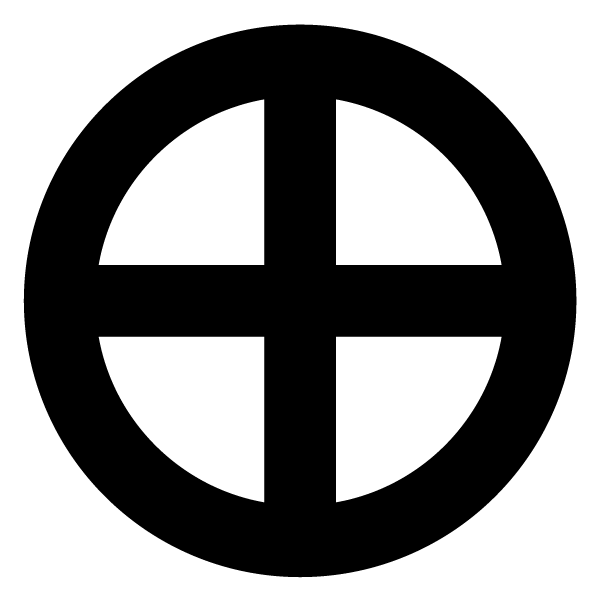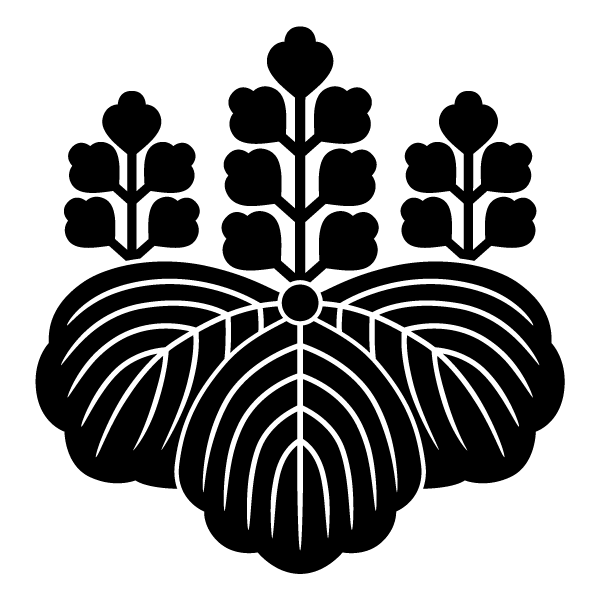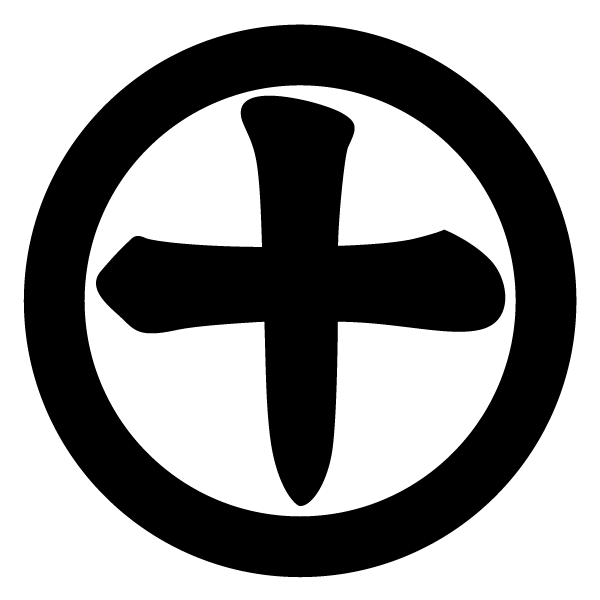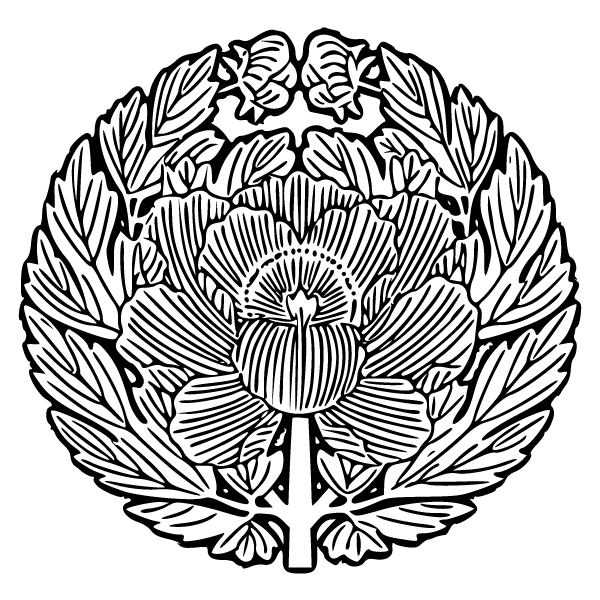祖の忠久を源頼朝の庶長子で惟宗氏の養子となった人物であると称するも、実際には忠久はもともと惟宗氏の出身であったらしい。日向・薩摩・大隅三ヶ国の守護職と薩摩国島津荘の地頭職を与えられた忠久は地名をとって島津氏を名乗るようになり、やがてその子孫が九州に下って地盤を形成していった。
歴史が古く、勢力も大きい島津氏であったが、内紛が続いていた時期が非常に長かった。しかし戦国時代初期、庶流の伊作家から出た忠良とその子。貴久によって島津氏は統一され、さらに貴久の子である義久・義弘・歳久・家久の4兄弟が九州地方を席巻して、あと一歩で九州を統一するまでに至った。
豊臣秀吉の九州征伐に敗れて臣従したが、薩摩・大隅と日向の一部を所領とすることを許された。秀吉死後の関ヶ原の戦いでは西軍に付いたものの、戦後の交渉で上手く立ち回ったために所領を安堵される。さらに幕府の許可を受けた上で琉球を従属下に置いて、計72万8千石の大大名として江戸時代に入った。
関ヶ原の戦いとその後の交渉における島津家の活躍ぶりは特筆すべきものがあった。秀吉の九州征伐にも頑強に抵抗し、朝鮮出兵でも活躍しただけに、徳川家康・石田三成ともに味方に引き入れようと苦心したようで、島津義弘が朝鮮から戻ってくるや否やすぐに家康による接近が始まり、これに対抗して三成も「豊臣家に忠誠を誓う旨、誓詞を出してくれ」と言いつのっていたらしい。
島津家中は、豊臣政権への帰属意識が薄かったせいか、家康に味方する方向で意見がまとまっていたようだ。ところが、関ヶ原の戦いで島津軍は西軍に参加してしまう。その原因は、家康との約束通りに兵を率いて意気揚々と中央に向かった義弘が伏見城へ入ろうとしたところ、徳川家の家臣に入城を拒否されてしまったせいだという。これで怒り狂った義弘が、西軍への参加を決めたのである。
どうしてこんなことになったのかはわからないが、情報伝達速度の遅い時代のこと、何らかの行き違いがあってもおかしくはない。なにはともあれ、西軍として関ヶ原の戦いに挑んだ島津軍だったが、ほとんど戦わないうちに合戦は西軍の敗北で終わろうとしていた(原因は三成と義弘の不仲であるとも)。
さて撤退となった時、義弘は常識をひっくり返す手段を選んだ。通常、撤退というのは後ろへ向かって行うものだが、島津軍は前へ進む。東軍のど真ん中、家康の本陣をかすめるようなルートで突っ走り、最後には八十人ほどになりながらもついに逃げのびてしまった。これを俗に「島津の退き口」という。
戦後、義弘は九州へ戻り、そこから3年にわたって島津家と徳川家の間で交渉が行われた。他大名のケースを考えればよくて減封、悪ければ改易となってしかるべきだったが、最終的には旧領安堵という島津家にとっては最高の結果に落着した。
これには、義久、義弘の子・忠恒(家久)らの交渉が功を奏して「義久らは関わっていない」ということが認められたことや、島津家の所領が南九州という近畿からも関東からも遠い位置にあったことなど様々な原因が背景として考えられるが、「関ヶ原の戦いでの島津勢の活躍があまりにも壮絶すぎた」ことが理由だったとしても、まったく不思議ではない。
ただ、この時期の島津家にまったく問題がなかったわけではない。実際には指揮系統の分裂、という大きな問題があった。秀吉に臣従した際に当主・義久が出家して、家督が忠恒に譲られるという複雑な経緯をたどったため、江戸時代の初期には義久・義弘・忠恒の三人が権力者として並び立つ「三殿体制」という不安定な体制とならざるを得なかったのである。一時期、この三者の関係が悪化して不穏な空気も流れたが、間もなく義久が病没したので大きな問題には発展しなかった。
島津家はほぼ唯一の転封を経験しなかった大大名であり、そのため薩摩藩は領内を百余りの外城に分けてそれぞれに拠点を置き、そこに住む地頭と城下士(郷士)に統治を行わせる、中世からの流れを汲む支配体制をとった。ただし、寛永年間以降には地頭は外城に赴かずに鹿児島城下に住むようになり、近世武士的な性格を持つようになる。
薩摩藩の統制は非常に厳しかった。たとえば宗教の面でいえば、キリシタン禁令は全国共通だが、島津家はこれに加えて一向衆(浄土真宗本願寺派)を禁止し、たびたび調査が行われてはこれに抵抗する動きがあったという。また、身分制度や職能という面でも薩摩藩の統制は厳しく、庶民が自発的に発展する傾向が乏しい代わりに、農民一揆などもほとんど起こらなかった。
薩摩藩は当初から経済問題を抱えている藩であった。軽石や火山灰で構成されるシラス台地が広がる薩摩領は貧しい土地柄であり、さらに火山の噴火や台風の直撃と自然災害の発生しやすい地理条件も重なって、表高よりもはるかに少ない収入しか得られなかったからだ。これに加えて7代・重年の頃には御手伝普請で宝暦の治水工事に駆り出されて財政的に大きな負担を被ることになった。
続く8代・重豪は「蘭癖」と呼ばれた人で藩校や医学館・薬草園を開き、オランダの品々を収集するなど開化政策を進めたが、これが薩摩藩の財政にさらなる悪影響を与えた。
9代・斉宣に代替わりした後、これに反撥する形で「近思録」派と呼ばれる集団らが政治改革を行おうとしたものの、重豪に弾圧され、改革は頓挫した(近思録崩れ)。この事件後に隠居へ追い込まれた斉宣に代わってその子の10代・斉興が家督を継いだが、実権を掌握したのは重豪であった。
こうした混乱と財政危機の中で登用され、財政再建を実現したのが調所広郷である。いわゆる天保の改革において彼は、商人たちに対して「借金は250年割・無利子で返す」という実質的な踏み倒しを敢行して借金を整理し、さらに奄美諸島の黒糖の専売や琉球貿易を拡大する政策によって、困窮していた薩摩藩財政を見事に救った。
重豪没後も調所広郷が藩政に大きな位置を占めたが、そこから「お由良騒動」が起きた。
斉興には嫡男の斉彬とその異母弟の久光がおり、両者同士の関係は良好であったらしいのだが、久光の生母で斉興側室のお由良の方と広郷が結託し、久光に家督を継がせようと画策したのである。広郷としては、重豪譲りの開明主義者である斉彬が家督を継承すれば、再び財政に悪影響を与えるのではないかと危惧したらしい。
しかし一方で斉彬には彼を擁立しようとする改革派の藩士たちがおり、両者の暗闘が過熱した末に老中・阿部正弘らの介入もあって、斉彬が11代目として家督を継ぎ、一件落着した。
藩主となった斉彬は養蚕・砂糖・紙・菜種といった特産物の奨励や、巨大工場群・集成館を中心として反射炉による小銃・大砲の生産や陶磁器・硝子・電信機などの生産や開発を研究させ、さらに造船事業も推し進め、来るべき動乱と開国の時代に向けて海防に心を配った。
斉彬の眼は藩内だけでなく幕政にも向けられ、日米修好通商条約と13代将軍・家定の後継者を巡る問題が持ち上がった際には一橋派の中心人物として幅広く運動を展開した。
これに先立つ形で養女の篤姫を家定の正室として送り込んでいたことはあまりにも有名である。
このような活動から斉彬は幕末四賢侯の一人に数えられ、また開明的大名の代表格とも見られた。ところが、幕政工作が失敗して14代将軍として徳川家茂が立った直後に病に倒れ、そのまま亡くなってしまう。
跡を継いだのは異母弟・久光の息子の忠義であり、薩摩藩の実権は「国父」久光がにぎることになる。彼もまた幕政に深く関与し、自ら江戸へ上って参勤交代の緩和など文久の改革を実現させ、公武合体路線で動乱をまとめようと画策したのだが、その帰路で行列を横切ったイギリス人を殺傷する生麦事件を起こしてしまう。これがきっかけになって薩摩藩はイギリス艦隊に攻撃され(薩英戦争)、外国の力を知って攘夷から親英へと路線を変更していくことになる。
もう一つ大きな要素となったのが長州藩との関係であった。薩摩と長州は京での主導権を巡る争いから犬猿の仲になっていたが、のちに坂本龍馬の仲介により和解し、薩長同盟を結んで討幕のために動いていくことになる。
こうした動きを主導したのが、かつて斉彬によって見出された西郷隆盛、あるいは大久保利通といった下級武士より登用された人材たちであり、彼らは王政復古の大号令・戊辰戦争を経て幕府側勢力を打倒し、新政府を樹立して新たな時代を築いていった。
その中心人物であった西郷隆盛は派閥闘争に敗れて薩摩へもどり、不平士族の反乱に担ぎ出される形で西南戦争を戦い、自決している。その際、久光・忠義親子は不干渉・中立を守ったという。