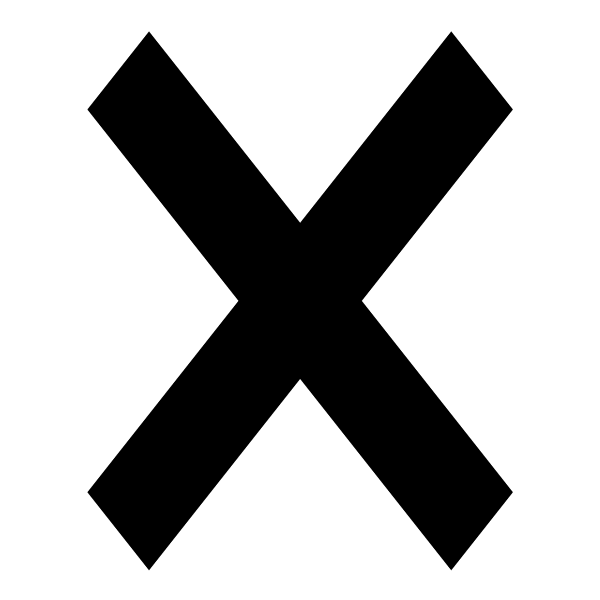関東に大きな勢力を築いた武蔵七党のひとつ児玉党(もとは藤原氏の末裔)の一族が尾張守護の斯波氏に仕える形で丹羽郡児玉村に住みつき、「丹羽」を名のるようになった――というが、このあたりの経緯ははっきりしない。
頭角を現したのは丹羽長秀の時で、織田信長の側近として活躍し近江国佐和山に5万石を与えられた。信長死後の織田政権内部での争いにおいては初期から羽柴(豊臣)秀吉を支持、厚遇されて120万石を与えられた。しかし長秀の死後にその子の長重が跡を継ぐと次々と所領を没収され、最終的に加賀と石川に12万5千石を与えられた。
ところが、長重は関ヶ原の戦いにおいて西軍に付き、東軍側に付いた北陸の大大名・前田家を抑える役目を担ったため、戦後に改易されてしまう。
しかし、以前から徳川秀忠と親交があったことが功を奏して古渡藩1万石として大名に復帰、さらに大坂の陣で戦功をあげて陸奥国棚倉藩5万石に、さらに白河藩10万7百石に、とたびたび加増・転封を受けた。最終的に、長重の子・光重の代に二本松藩10万石に入り、そのまま幕末までこの地に定着した。
二本松藩の藩政は2代・光重、3代・長次の頃に確立され、凶作などもあったが一応の安定を見せた。一方でこのふたりは学問の振興にも熱心であり、学者を招いて「家塾」を建てさせたりした。今でも、二本松市には現存する最古クラスの算額(数学の問題を解いてその結果を奉納するもの)が残されており、学問が盛んであったことを偲ばせる。
東北諸藩のほとんどがそうであったように、二本松藩もまた度重なる天災や御手伝普請などによって経済的に困窮するようになり、享保の頃よりたびたび藩政改革に取り組んだ。
儒学者・岩井田昨非は「自分の名前をきちんと書ける藩士は10分の1以下だった」という二本松藩を改善するために、藩士たちに文武を学ばせ、新たな人材を探し、さらに綱紀粛正を行った。財政問題に対しては税を増やし、厳密にこれを取り立てることで解決したが、あまりにも強引だったために多数の反撥を受けた。
これに対して昨非は「爾俸爾禄 民膏民脂 下民易虐 上天難欺(お前たちの俸禄は農民たちの膏であり脂〈=血と汗の結晶〉であるのだ。農民たちを虐げることは簡単だけれど、そんなことをしようものなら天を欺くことはできないぞ)」という戒石を建てさせ、自分の意思を表明しようとした。
ところが、この内容が農民たちの間で「農民たちは欺きやすいもので、虐げても民の血と汗を絞り、お前たちの俸禄にしろ」という意味なのだ――と誤解が広まり、当時凶作にあえいでいた農民たちの怒りに火をつけ、大規模な一揆を招いてしまった。そこで昨非は自ら一揆鎮圧に乗り出し、戒石の意味がまったく逆であることを説いた。これを聞いた農民たちの中には涙を流す者さえあり、一揆は収まった。しかし昨非はこの騒動の責任を取らされ、失脚した。
ただ、昨非の改革への反撥と彼の失脚については、「改革反対派の陰謀」という説がある一方で、「昨非は税を増やすばかりで生産力を増やそうとしなかった」と改革の欠点を指摘する向きもある。
こののちにも寛政期や天保期などに改革が行われ、様々な政策が実行された。しかし、たびたびの天災や飢饉、幕府が行う工事のための出費などで財政はさらに困窮し、大規模な一揆もあって、大きな成果をあげることはできなかった。
戊辰戦争では奥羽越列藩同盟に参加し、各地で戦ったが敗北を繰り返した。幕末期に出兵・警備の任務を繰り返したことで財政がさらに悪化し、旧式の軍備しかできなかったのが原因であったという。
いよいよ新政府軍が二本松城に攻め込んだ際には主力は別方面で戦っており、二本松少年隊と称される少年兵が必死の防戦をしたもののかなわず、多大な被害を受けた。二本松城は炎上し、藩も降伏。五万石に削られ、明治時代を迎えることになった。